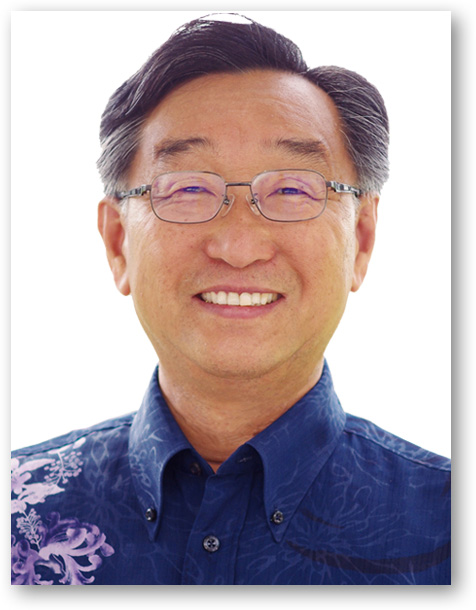質問・答弁を動画で視聴できます。
【概要】エッセンシャルワーカーの処遇改善、人手不足解消へ
〇社会の基盤を支える働き手とその意義
〇低賃金や長時間労働の是正
〇訪問介護の危機打開へ
〇燃料費等、市内民間事業者への支援を
〇公共事業の質向上と公正な労働条件につながる公契約条例
〇農業の魅力を活かした新規就農支援
◯高村直也議員
日本共産党の高村直也です。エッセンシャルワーカーやケア労働をめぐる問題について一般質問します。
2019年末からコロナ禍が急速に広がった際、感染症の拡大を防ぐため、不要な外出を控え、社会的な活動を様々に制限することになりました。そうした中でも、外出を控えず、働かなくてはならない存在として、エッセンシャルワーカーが国内外で注目されました。
日本の厚労省も、社会機能維持者や、緊急事態宣言下でも事業の継続が求められる分野という言葉を使い、必須の労働者、エッセンシャルワーカーに当たる事業者を具体的に示しました。
幅広い分野が対象になりましたが、中でも特徴的なものとしては、感染症対策の最前線に立つ医療、介護、保育などのケア労働者や、食料やコロナワクチンなどの必需品を運ぶトラック運転手、スーパーマーケットの職員などのブルーカラー労働者があります。ドイツでは、当時の文化大臣がアーティストは生命維持に必要不可欠と断言するなど、音楽家や芸術家、作家などもエッセンシャルワーカーに当たるとして、さらに広い定義を採用しました。
リスクを冒して大変な労働の下に働いている、これらの労働者がいなくなったら社会が成り立たなくなるということで、コロナ禍において尊敬や激励の声が広がりました。
最近では、能登半島地震からの復興をめぐってもエッセンシャルワーカーの重要性が浮き彫りになっています。石川県が今月発表したところによると、今年度、国や自治体による復興関連の公共工事において四十八件の入札不調があったとのことです。幹線道路や保育所など暮らしの基盤となるインフラの復旧が進まない深刻な事態ですが、背景には、資材の高騰などのほか、建設労働者の人手不足があると指摘されています。
エッセンシャルワーカーの重要性や役割について、市長の御認識を伺います。
社会の基盤を支える、不可欠な存在であるエッセンシャルワーカーですが、その持続可能性が問われています。コロナ禍で役割を果たし、尊敬されたはずの分野ですが、依然として人手不足や高齢化、低賃金や長時間労働などが問題になっています。
ケア労働はその労働の質を数値や金額で評価することになじまず、公的な機関や保険制度を介した支払いが多いことが特徴です。また、エッセンシャルワーカーに該当するブルーカラー労働も、機械などで置き換え難い、様々な人的配慮を必要とするという点でケア的な側面があると言えます。そのため、人が担う労働の値打ちに対して正当な評価がされず、低い賃金のまま固定化してしまう傾向があります。
例えば保育の仕事は、単に子供を見守るだけでなく、一人一人の言葉、運動能力、社会性などの発達段階を見極めながら適切に関わることが求められます。まだ自分の意思を言葉で伝えることができない子供に対しては、言葉ではなく表情やしぐさから気持ちを読み取って対応し、自己表現ができるようサポートする必要があります。
このような仕事は単純にAIやロボットには置き換えられません。子供の気持ちを酌み取り、安心感を与えながら成長を支えるのは、人間だからこそできることです。エッセンシャルワーカーの仕事をしっかりと評価し、賃金に反映することが重要です。
賃金を引き上げることの重要性は、今や広く認識されています。一昔前は、国際競争力を強化するためとして賃金を低く抑えることが叫ばれていたこともありました。しかし、この間は政府も、企業は投資や賃金を抑制し、家計は所得の伸び悩みなどから消費を抑制する、コストカット型経済に陥っていることとともに、賃上げの重要性を指摘しています。
とりわけ人手不足に陥っている分野であるエッセンシャルワーカーの仕事で賃上げが行われれば、他の業種でも人材を確保するために賃上げをする圧力にもなります。この点でもエッセンシャルワーカーに対する賃上げは重要です。
社会を持続可能なものにしていくためにも、エッセンシャルワーカーの処遇改善を進めていくべきですが、いかがでしょうか。
当面する人手不足による問題への対策としては、処遇改善で人手を確保する以外にも、AIやデジタルを活用して仕事を効率化することが挙げられます。しかし、企業は、効率化が進めば進むほど人件費を削ろうとする傾向にあります。AIやデジタルの導入は短期的には労働時間を短縮できますが、そのことによって長期的には賃金が下がってしまうことが懸念されます。
AIやデジタルの導入を進めるに当たっては、賃上げや待遇改善が適切に行われなければ、さらなる人手不足やコストカット型経済に陥ってしまうリスクがあると考えますが、いかがでしょうか、御認識を伺います。
続いて、具体的な仕事の分野について質問します。
このほど、訪問介護が危機的な状況に陥っています。東京商工リサーチの調査によると、昨年、倒産や休廃業、解散した訪問介護事業所が529社と過去最高になりました。以前からの逼迫した状況に加え、昨年4月から国が介護基本報酬を2から3%下げたことによるものと考えられます。
私も、当事者から切実な実態をお聞きしています。利用者を訪問するためのガソリン代など物価高騰の影響が深刻な中、基本報酬も下げられ、訪問介護をしても利益が出ない、やむなく訪問介護の事業をやめることになった事例があるなどというものです。
仙台市では昨年、訪問介護事業所の倒産は0件でしたが、人手不足などを背景として、訪問介護事業の廃止手続をする事業者が3件ありました。本市の実態調査でも、基本報酬引下げについて影響があると答えた事業者が50件中17件ありました。
介護の分野における人手不足の実態は深刻です。厚労省の一般職業紹介状況や社会保障審議会の資料によると、介護全体の有効求人倍率が昨年は3.89倍、訪問介護では2023年に14.14倍にもなっており、圧倒的な人手不足です。
介護職員の賃金は、令和5年賃金構造基本統計調査によると、全産業平均と比べて月6万円ほど下回り、低賃金の下に置かれています。そうした中、新潟県村上市は、訪問介護基本報酬の引下げによる減収分を、昨年四月改定時に遡って独自補助することを決めました。報酬引下げによる減収分を事業所に補填するとともに、ガソリン代を車1台につき月3000円支給し、利用者宅まで7キロ以上の訪問介護に1回50円上乗せします。
本市も、訪問介護基本報酬引下げによる減収分を補填する独自補助を行ってはいかがでしょうか。また、報酬引下げ撤回を国に強く求めるべきですが、いかがでしょうか、併せて伺います。
さらに、人手不足解消のためにも、若手職員への給与上乗せ補助や宿舎借り上げ補助といった処遇改善を本市独自で実施すべきです。いかがでしょうか。
保育士の処遇改善をめぐっては、賃金を平均で10.7%引き上げる補正予算案が昨年12月、国会で可決しています。一方、厚労省の白書に示されている保育士が離職する理由の上位には、給料が安いことと並んで、仕事量が多い、労働時間が長いことが挙がっています。多忙さを解消し、子供たちに行き届いた保育を保障するためにも、保育士の配置基準を改善することが求められます。
このほど国が基準を見直しした三歳児や四、五歳児だけでなく、新潟市や横浜市で取り組まれているように、ゼロ歳から二歳児も含め市独自で配置基準を改善すべきです。いかがでしょうか。
続いて、エッセンシャルワーカーに該当するブルーカラー労働者についてです。
宮城県トラック協会は、2022年6月、本市に対し、燃料価格の高騰などで事業の運営に支障が生じているとして支援を求める要望書を提出しました。これを受け本市は、翌年、貨物自動車運送事業への燃料費助成を実現することになりました。この要望書の中でも、同業界の皆さんが物流の安定やワクチン接種の配送などに取り組み、エッセンシャルワーカーとして役割を果たしてきたことが明記されています。
岩手県は、社会インフラとして重要な運送業者の維持と確保を図るためとして、貨物自動車運送事業を営む事業者に対し、支援金の支給を今年も実施しており、同支援金は既に第五弾を数えています。本市も、運送事業者をはじめ、市内事業者への燃料費などの助成を行ってはいかがでしょうか。
本市は、公共施設などの建設工事や施設を清掃する業務を民間事業者に発注しています。また、ごみ収集などの分野ごとに、本市の各当局が民間事業者に委託する業務もあります。これらはエッセンシャルワーカーに該当する仕事と言えます。本市が直接発注している事業であるわけですから、まずそこから公正で模範となるような雇用関係を築いていくことが重要です。
政令指定都市の中でも、相模原市、川崎市、京都市は、独自で公契約条例を創設して、賃金や労働条件などの水準を保つ仕組みをつくっています。
ところで、公契約条例をつくる意義は雇用に関わることだけではありません。日本建設業連合会は、2009年に下請は原則3次以内という基本方針を示しています。こうした理念を実現すべく宮城県は、2020年から、労働者の多重下請について調査、改善をすることを目指したモデル工事を実施しています。その実施要領には、土木一式工事は原則2次下請まで、建築一式工事は原則3次までとすることなどが定められています。
本市が発注する建設工事にはこのような縛りがありませんが、公契約条例が実現すれば、多重下請によるピンはねや工事の質の悪化などを防ぐことにもなります。本市として公契約条例をつくるべきですが、いかがでしょうか。
本市交通局が担う市バス運転士も、地域の足を支えるエッセンシャルワーカーです。道路の状況やダイヤ、交通安全に細心の注意を払い、苛酷な暑さや寒さに耐え、車椅子のお客さんがいればスロープを用意し、車内ベルトを固定するなど、乗客一人一人へのケアも担います。夜勤もあり、睡眠時間を十分に確保できない実態もお聞きしています。そうした下で、人手不足や高齢化が問題になっています。
交通局の職員の中でも、一般職とバス運転士の賃金がそれぞれ異なる給料表に基づいて決まっています。そのことにより、正職員のバス運転士であっても、一般職とは年収の平均で100万円以上の大きな差があります。これには、かつて経営健全化を理由に、市の行政職給料表である一表をバス運転士の二表に変更したという経過があります。
バス運転士の給料表を一表に戻し、正職員と会計年度任用職員の処遇改善をすべきですが、いかがでしょうか。また、正職員の運転手を積極的に採用し、割合を増やすべきですが、いかがでしょうか、併せて伺います。
厚労省が示した社会機能維持者、エッセンシャルワーカーの分野には農業も含まれます。
今月3日に開催された仙台市農業委員等と私たち議員の意見交換会では、農業従事者の数の減少により懸念される内容の一つとして、農地周辺において共同で行われている草刈りや農業用水路の維持管理をする人が減ることが挙げられました。ひいては、農地が荒れ、農村のコミュニティーが崩壊するのではないかと指摘がありました。
こうした問題は、農業の生産が幾ら効率的に運営されることになっても、それだけでは解決しません。農業における多面的機能の中でも、コミュニティーにおける人と人とのつながりをつくる様々な活動、言い換えればケア的側面について重要性を指摘したものと言えます。この点を尊重する姿勢が重要だと考えますが、当局の御認識を伺います。
人手不足が深刻な問題となる中ですが、農業をやってみたいという若い世代の意識は高まっています。JAによる昨年12月のアンケートでは、将来、農業をやってみたいという20代の回答は52.1%にも上りました。農業の魅力としては、自然と向き合える、自分と向き合える、成果や過程が目に見えるが上位を占めました。これは農業のケア的側面が注目されているということでもあると思います。こうした広範な若い世代に対して農業への門戸を開くことはいよいよ重要です。
福島県では、県と3つの農業団体、JA、県農業会議、県農業振興公社がワンストップ、ワンフロアで就農前から農業経営発展までをサポートする相談窓口が開設されました。宮城県でも同様の相談窓口はありますが、例えば、みやぎ農業振興公社が就農するまでの段階でのワンストップのウェブ窓口を開設するなどにとどまっています。
意欲を持った若者が、就農後、収入の安定といった課題もあり、挫折して離農するケースも多い中、経営発展までサポートする体制は重要です。本市としても、宮城県と相談してより充実したワンストップの相談窓口の開設を目指すべきですが、いかがでしょうか。最後に伺って、第一問といたします。
◯市長(郡和子)
ただいまの高村直也議員の御質問にお答えを申し上げます。
エッセンシャルワーカーの重要性や役割についてでございます。
いわゆるエッセンシャルワーカーの皆様は、福祉や医療、物流など、市民生活や社会基盤の維持に不可欠な役割を果たしておられます。
コロナ禍を振り返りますと、我々の暮らしを守って、社会経済活動の停滞を食い止めるために懸命に御尽力をいただいた姿には、多くの市民の皆様が感銘を受けるとともに、改めて重要な役割を担っていただいていることを実感いたしました。
人口減少や高齢化が進む中で、こうした方々の重要性は今後ますます高まるものと認識しておりまして、今後とも、地域を支える人々が誇りを持って活躍できる環境を整え、市民の皆様が暮らしやすいまちづくりを共に進めてまいりたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、交通事業管理者並びに関係の局長から御答弁申し上げます。
◯財政局長(永渕智大)
私からは、公契約条例に関する御質問にお答えいたします。
本市発注の工事等における下請は、地元企業の受注機会の確保や業務内容の高度化への対応などから必要と考えておりますが、行き過ぎた下請構造は労務費へのしわ寄せ等の懸念があるものと認識をしてございます。
一方で、労働者の労働条件の確保は全国的な労働政策に係る問題であり、公契約条例によって本市発注業務に従事する労働者のみを対象とする制度を設けることには慎重な対応が必要と認識をしてございます。
引き続き、国の一括下請の禁止等の取組の徹底を図りますとともに、適正な予定価格の設定や低入札価格調査制度などの契約上の取組を通じて、下請を含めた受注者の労働環境の適正化に努めてまいります。
◯健康福祉局長(郷湖伸也)
まず、訪問介護報酬の減収分への補填及び処遇改善についてお答えをいたします。
介護事業者の経営は介護報酬により賄うことが基本であり、本市では、訪問介護事業者の職員待遇や経営状況を勘案の上、安定的な事業運営に必要な報酬水準を設定するよう国に要望を重ねてまいりました。
本年度、若手職員を含む処遇改善加算の引上げに加え、国の補正予算でさらなる改善等の措置が講じられることから、本市独自の補助は考えておりませんが、引き続き、こうした支援策の活用を促すとともに、処遇改善と安定した事業運営が可能となる適切な報酬水準の確保について国に求めてまいります。
次に、訪問介護における基本報酬引下げへの対応についてでございます。
令和6年度の報酬改定では、国の介護事業経営実態調査において訪問介護の利益率が介護サービス全体の平均を上回ったため、基本報酬が画一的に引き下げられたところです。
一方、報酬改定後の事業所ヒアリングでは、施設併設型とそれ以外の訪問介護事業所の違いなど、実情を踏まえた報酬設定を求める意見もいただいております。
本市としては、継続的に事業者から実情をお伺いしながら、経営実態などを踏まえた報酬体系の設定や財政措置について、国に対し求めてまいる考えでございます。
◯こども若者局長(郷内俊一)
私からは、保育士の配置基準の改善についてお答えいたします。
保育の質を高め、保育士の労働環境を向上させるためには、配置すべき保育士の人数を見直すことは有効であり、これまでも機会を捉えて国へ要望を行ってまいりました。
配置基準の改善は、保育士の確保が各施設において円滑に行われるよう、給与水準の引上げなどの処遇改善と一体で進める必要があるため、国の責任において検討すべき事項と考えております。
国のこども未来戦略において一歳児の配置基準を改善する方針が示され、現在検討が進められており、この動向を注視するとともに、国に対しては、引き続き保育士の確保策の充実と併せて必要な要望を行ってまいります。
◯経済局長(木村賢治朗)
経済局所管の御質問のうち、市長からお答えしたもの以外についてお答えいたします。
まず、エッセンシャルワーカーの処遇改善と人手不足への対応についてでございます。
本市では、国の交付金も活用しながら、関係局においてそれぞれの分野を対象とする支援を実施してきたところでございまして、経済局でも、雇用主である事業者が賃上げの原資を確保できるよう、物価高克服・賃上げ応援パッケージ等を通じて、生産性向上など収益力を高める総合的な支援を進めてまいりました。
今後とも、事業者に対する人材確保や働きやすい職場環境づくりなどの支援と併せて、市民生活に不可欠な幅広い業種の事業継続を支えてまいりたいと存じます。
次に、市内事業者への燃料費等の助成についてです。
燃料費や原材料費が高止まりする中で、事業者が将来にわたり事業を継続していくためには、生産性を高め、収益力を強化することが重要と認識しております。
本市ではこれまで、国の交付金も活用しながら、物流事業者の省力化等にも資する支援などを実施しているところでございまして、こうした取組を着実に進めることで市内事業者の事業継続を後押ししてまいりたいと存じます。
次に、農村のコミュニティーについてでございます。
高齢化や過疎化の進行などにより担い手不足が顕在化する中、農村地域におけるコミュニティーの維持や活性化は重要な課題であるものと認識しております。
本市では、これまで、国の交付金を活用し、農業者に加え、地域の自治会など農業者以外の方が農地の草刈りや水路の泥上げなどの共同活動に参加した場合、その活動に対する支援を行っているところでございます。
今後とも、地域が協力しながら取り組む共同活動への支援を通じ、農村地域のコミュニティーの維持や活性化に取り組んでまいりたいと存じます。
最後に、ワンストップ相談窓口の開設についてでございます。
本市では、宮城県、JA仙台、農業委員会等の関係機関と連携し、就農に関する毎月一回程度の就農相談会を開催しております。この相談会では、栽培技術や農地の借入れなどの助言を行っております。
加えて、随時、こうした関係機関と共に営農計画の策定や就農後の経営指導等の伴走型支援も行っているところでございまして、引き続き就農者の相談内容に応じた支援に取り組んでまいりたいと存じます。
◯交通事業管理者(吉野博明)
私からは、市バス運転士に係る2点の御質問にお答えを申し上げます。
まず、その給料表についてでございます。
公営企業職員の給与は、地方公営企業法において、同一または類似の職種の国や地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営状況等を考慮して定めなければならないとされております。
交通局では、国や民間事業者との均衡を図るため、運輸職員について給料表第二表を導入したものでございます。他の政令市等の公営交通事業者においても、運輸職員には独自の給料表が適用されている状況にございます。
引き続き現行制度を運用する中で適切な処遇確保に取り組んでまいります。
次に、正職員採用についてでございます。
本市バス事業におきましては、厳しい経営環境を踏まえ、現在の給与体系や職員採用制度を構築してまいりましたが、全国的に運転士人材不足の中で、事業運営に必要な人材を確保する上でも処遇改善の視点も重要と考えております。
そのため交通局では、令和2年度当初で7割弱となっておりました運転士の正職員割合を今年度には約8割まで拡大をしてきております。今後とも、経営面とのバランスを考慮しながら、人材の確保に向けまして必要な取組を進めてまいる考えでございます。
◯高村直也議員
御答弁ありがとうございました。
市長からも、コロナ禍で懸命に取り組んだという評価ですとか、それから人口減少の局面の下でますます重要性が高まるというふうな御指摘もいただきました。であれば、市としてより踏み込んだ取組をしていただきたいというふうに思います。それから、賃上げの応援パッケージの紹介もありましたけれども、エッセンシャルワーカーというのは効率化になじまない職種だというのが特徴だということは第一問でも指摘させていただきました。効率化になじまないから、なかなか賃金が低賃金のまま固定化されやすいんだと、このことも指摘させていただいた上で、2点再質問いたします。
訪問介護事業所の経営は危機的な状況にあります。基本報酬の補填については、国のほうに要望したいというふうな御答弁もありました。
コロナ禍を経て、厳しい条件の中で訪問介護を担ってきた人たちが、報われるどころか、基本報酬引下げで苦境に立たされるという理不尽なことが起こっています。事業者の方から本当に切実な悲鳴のような声を聞いておりますので、本市としても何らかの支援に踏み出すべきではないか、基本報酬の補填に踏み出すべきではないかということで、再度伺います。
また、働く人に行き届く支援も必要だと思います。国が昨年6月実施した処遇改善があるわけですけれども、事業所の経営面から見ると、逆に負担増となる場合もあるというふうな形になっているんですね。ですから、本市が保育士の皆さんにやっているように、市独自で直接介護職員の賃金に上乗せした支援を今こそ実施すべきではないかということで、この点も伺います。
◯健康福祉局長(郷湖伸也)
訪問介護事業所に関する再度の御質問にお答えをいたします。
近年、市内の訪問介護事業所は廃止件数を新規指定件数が上回っておりまして、令和2年度、市内の訪問介護事業所、244事業所でありましたのが、本年2月現在で274事業所と増加傾向にございます。
また、今年度、国の報酬改定を踏まえまして、事業所への実地指導の機会を活用して報酬改定による影響に関するヒアリングを行った50の事業所のうち、議員御指摘のとおり経営に影響があると答えられた事業所は17ございました一方、22の事業所からは影響がなかったとの回答もいただいているところでございます。
国の報酬改定の影響については、継続して実態を把握していく必要があると私どもも考えておりまして、その結果も踏まえながら国への要望に反映してまいりたいと、そのように考えております。