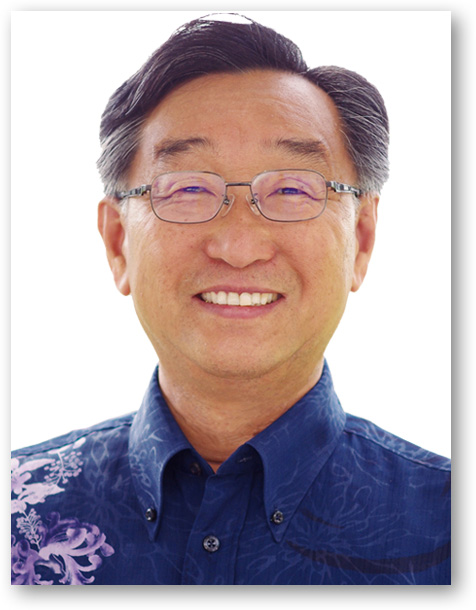質問・答弁を動画で視聴できます。
【概要】小中学校の教員の働き方を改善させよう
〇「定額働かせ放題」の教職調整額はやめて残業代の支給を
〇8時間労働を基本に教職員を抜本的に増やそう
〇35人以下学級から30人、25人学級へ
〇特別支援学級の定数を6人に、市独自に踏み出そう
〇スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの各学校への常勤配慮
〇養護教諭や学校事務職員は複数配置に
◯ふるくぼ和子議員
日本共産党仙台市議団のふるくぼ和子です。子供たち一人一人の学びの保障となる教員の働き方の改善について一般質問を行います。
教員の多忙化に焦点が当てられ、働き方改革が叫ばれ、本市においても様々な負担軽減策が行われていますが、抜本的に改善しているとは言えない状況が続いています。
文部科学省の教員勤務実態調査によると、2022年の持ち帰り残業を含む教員の平均勤務時間は、小学校で平日11時間23分で、週当たりの勤務時間は59時間19分、中学校でも平日11時間33分で、週当たりの勤務時間は63時間59分にも及んでいます。こうした働き方の下、心身を病み、精神性疾患による病休者は増加の一途をたどり、2023年には7千人を超え、過労死も起きているとのことです。
仙台市でも決して例外ではありません。朝、出勤し、授業を行うことはもちろん、業間休みは子供の対応があればトイレに行く休憩時間さえままならず、昼食は給食指導で子供と一緒に配膳し、片づけまで対応し、子供たちの下校後には提出物の確認や丸つけ、次の授業準備に会議に校務事務などなど、一段落して時計を見るともう午後7時過ぎという勤務が、多くの学校で特別なことではなく行われている、これが教員の働き方の実態です。
こうした中、教員は授業準備や子供たちと向き合う時間がないと訴え、子供たちや保護者からは、先生が忙し過ぎて声をかけられないとの声が上がっています。教員の労働問題にとどまらず、子供たちの学びと成長にも大きな影響を与える問題として、直ちに改善しなければなりません。市長は、市の職員として働く現在の市内小中学校における教員の実情をどのように理解し、お考えになっているのか、教員の働き方は本来どのようであるべきとお考えなのか、御見解を伺います。
教育委員会では、2022年度から2024年度までの教職員の働き方改革取組指針を定め、今年度末までに、正規の勤務時間以外の在校等時間を3年間で一人当たり1か月平均10時間の減少と、教職員の年次有給休暇の取得日数を1年間平均12日以上という2つの目標の達成を目指すとしています。まず、達成状況と見込みについて伺います。
取組指針の教職員の皆さんへと冒頭に呼びかけている文書には、働き方改革の必要性について述べ、勤務時間、休暇等に関する規定を改正したことや、92項目にわたる働き方改革に関する施策に取り組むとともに、学校における働き方改革を進めるための取組事例集を取りまとめ、各学校に周知し、積極的な活用を呼びかけるなど、教職員の勤務や職場環境の改善に取り組んできたとあります。そして最後に、教職員の皆さん一人一人がこの趣旨を理解し、率先して各学校の実態に即した取組を行っていただきながら、働き方改革をこれまで以上に推進していきましょうと結ばれているのですが、教員の努力で行われるものなのかと大きな疑問を感じます。
もちろん、教員が働きやすい環境がどうであるかを出し合い、職場づくりを行うことは重要です。しかし、学校現場からは、負担が減ると言ってシステムが変わっても、そのシステムに慣れるまでが大きな負担、負担軽減と言いながら新しいことが持ち込まれると報告が求められることもしばしばで、逆に仕事が増えている気がするという声が届いています。市の考える教員の働き方改革が長時間労働をつくり出し、逆効果になっていないかの検証が必要ではないでしょうか、伺います。
取組指針で定めた目標値との関係でも、時間外在校等時間も年休取得についても先生方の状況に明らかな変化は見られませんので、目標には遠く及んでいないであろうことは明確です。現場からは、膨大な周辺業務が必要となる標準学力検査や子ども体験プラザなど、悉皆でやることの教育効果に疑問の声が上がり、新たな業務が持ち込まれることに疑問を呈しています。そうした業務を具体的に減らすことなく、どうやって教員の働き方改革を徹底していこうというおつもりなのでしょうか、お聞かせください。
また、新年度から2029年度までの期間で次期取組方針を作成するとしていますが、抜本的な業務の見直しを行うことを明確に打ち出すべきです。併せ伺います。
教職員の働き方改革を本気で進める気があるのであれば、まず一つに、長時間労働を改善する取組が必要です。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、いわゆる現行の給特法は、1971年に当時の全野党の反対を押し切って強行されましたが、教員の本給に教職調整額を上乗せ支給することで、残業代制度を外してしまいました。
残業代制度は長時間労働を抑えるための世界のルールで、日本においても労働基準法で全労働者に適用されています。残業に割高な賃金支給を義務づけることで使用者のコスト意識に訴え、業務の削減や長時間労働の改善につなげようというものです。
ところが、教員には、1966年の国の勤務実態調査による超過勤務時間数を基に計算された教職調整額4%が、50年以上見直されることもなく現在まで適用されています。何時間残業しても残業代は出ず、全て4%の中に吸収されてしまう、まさしく残業代ゼロの定額働かせ放題となっています。結果、超過勤務時間として教職調整額と超過勤務手当額を比較計算をした場合、差額が1か月およそ10万円にもなるとのことです。
現在、国において教職調整額の引上げが検討されていますが、毎年1%ずつ、6年掛けて10%にするというもので、解決すべき課題に向き合っているとは到底感じられません。それどころか、政府は、新年度予算で1%引上げのために22億円を計上するその財源に、教員の手当など11億円を削減しようとしています。
長時間労働そのものをなくす努力と併せ、給特法の公立学校の教員には残業代は支給しないという条文を廃止すること、労働基準法第三十七条の残業代支給を適用し、給与が下がらないように教職調整額は本給に組み込むなど、全ての教員に対する正当な給与体系とするのが本来の在り方だと思いますが、国に求めるとともに、御当局の御所見を伺います。
もう一つのより抜本的な解決の道は、教職員を思い切って増やすことです。教員基礎定数の算定の考え方として、小学校であれば教員の受持ち授業は1日4コマとされ、1958年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、いわゆる義務教育標準法で、それに見合う基礎定数が配置されてきました。一日の労働のうち4時間は4コマの授業と休憩等に、残りの4時間は授業準備やその他の校務に充て、1日8時間労働を守ろうというものですが、もともとこうして教員の働き方が示されていました。
ところが、現状は、小学校でも道徳の教科化や小学校英語など新たな業務が増え、1日5コマ、6コマが当たり前となっています。1日に6コマの授業を行い、休憩時間も法律どおりに取れば、授業準備や様々な校務に充てられる時間は、定時の退勤まで僅か25分しかないことになります。週休2日になった時点で1日の持ちこま数が増えることが分かっていたはずですが、その際にも定数増は行われませんでした。こうして受持ち授業が増えることで、残業時間が増え、長時間労働が常態化してきたのが実態です。
ところが、国は、現場が最も強く求めている教職員定数の拡充には背を向け、何と新年度予算案には増えた分を差し引いて九千人近い削減を盛り込みました。本市の新年度の教員定数の内訳で見ても、通常学級を担当する教員は、児童生徒数の減で42名の定員が減ることになっています。給特法に手を入れることも当然だが、金より何よりとにかく現場に人を増やしてほしいと悲鳴が上がる学校に対して、これではあまりにも厳しい仕打ちと言わざるを得ません。今回の国の予算案に対しても、教員の定員増で現場にもっと人をと市は声を上げるべきですが、伺います。
市内の小中学校では、教員の病休や育休などで学級担任が不在になったまま教員を配置できない学校もあり、教員の配置には常日頃から御苦労されているものと思います。教員志望の学生が別の進路を選び始めている今、このままでは学校がもたなくなる切迫した事態に来ているという認識での対応が求められています。
今年度の市の職員定数条例では教員の職員定数は5294人ですが、現員数は5125人にとどまり、現員数の中でも定数に数えられる教員は4897人ですから、397人が空き定数となっています。これは今年度に限ったことではなく、毎年こういう状況で、新年度も419人の定員が充足しないままと見込んでいます。こうしたことを背景に、学校で病休などの欠員が出た場合、講師で継ぎはぎして埋めるということが繰り返されています。市の決めた定数をちゃんと充足させて正職の教員で配置すべきですが、いかがでしょうか。定数は上限を決めたものなどという言い訳はせず、定数条例で決めた数から逃げずにお答えください。
長期の病休や育休などでは、代替教員が講師であっても配置する努力が行われていますが、短期間の病休や男性教諭の育児休業などに対する現場対応は、少人数や理科などの専科で配置された教員を充てるなどが常態化しており、教員の持ちこま数を減らす効果が奪われています。学級担任ができる教員を根本的に増員することが求められています。
本市がこれまで35人以下学級を国に先んじて実践するなど努力してきたことは評価するものです。しかし、国が中学校まで35人以下学級としてきたことで、今後は国の基準どおりでいいとはなりません。教員の配置については、義務教育標準法でも自治体独自の人員配置は妨げていません。市として、学校においても八時間労働を基本に、授業の受持ちコマ数を1日4コマを基本とする考え方による教員配置をしてはいかがでしょうか、伺います。
また、35人の学級編制をさらに前進させ、30人、25人にしていくことや、1クラスの担任を2名にするなど、ほかにも教員の働き方の改善と子供たちの学校生活の充実のためのいろんな方法があると思います。市長は、どれが最も仙台らしさを発信する教育環境整備としてやれる、やりたいとお考えになるでしょうか、伺います。
今、緊急に求められているのが、特別支援学級の定数改善です。市も現在の8人を6人にと国に求めていますが、改善が図られないまま経過しており、現場ではもはや待ったなしの課題となっています。新年度は、特別支援学級数の増加に伴って26人増やすとしています。しかし、これまで、8人のクラスに1人増えることで学級数が増え、1クラスの人数も5人と4人の2クラスになるなど、一定の改善が見られる場合もあるものの、根本的改善につながるものではありません。
国に求め実施させることはもちろん大事ですが、今、目の前にいる子供と教員に対して、市は何ができるかが問われています。35人学級での実績もあるのですから、国に先んじて6人定数で教員を配置し、一人一人の子供の特性に応じて配置されている支援員は減らすことなく、特別支援を必要とする子供と教員のために市が決断をすべきときです。伺います。
教員の長時間労働の解消にも効果が期待されるのが、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなど教員以外の専門職や、養護教諭や学校事務職員の役割です。これまでもスクールソーシャルワーカーやカウンセラーを位置づけ、充実してきた努力を評価するものです。しかし、時々あるいは必要に応じて学校に来るスタッフということでは、その力を十分に発揮できないだけでなく、子供や教職員との信頼関係をつくることも困難です。日常的に教員との連携ができ、子供を見守り支える専門スタッフとして、各学校への常勤化を目指すべきですが、いかがでしょうか。
また、養護教諭や学校事務職員は、一定規模以上となれば複数配置になりますが、基本は一人職場です。養護教諭は、保健室をよりどころにする子供たちや校内でのけがや病気に対応するだけでなく、児童生徒の健康面から支える重要な業務です。しかし、一人しかいないので、保健室に鍵がかかっているという事態がどうしても発生します。そうすると、教頭先生や職員室で別の仕事をしている教員が対応することになって、教員の負担が増える関係です。職員室に余裕のある教員などいないことは、教育局が一番把握しているはずです。養護教諭と教員の両方の労働改善のためにも、学校の規模にかかわらず、養護教諭は各校2名以上とすべきです。伺います。
学校事務職員についても、複数配置にすることで、一人職場による負担が減ると同時に、教員の事務負担軽減を図ることができるのは明らかです。学校給食の食数や教材費の発注管理など、教員という資格がなくてもできる事務的業務を切り離すことで、教員の負担を軽減できるようになります。教員の本分である子供と向き合う時間を保障することが、御当局が何より大事にするべきことであり、やらなければならない仕事なのではないでしょうか。事務職員の複数配置も市の判断でできるのですから、決断を求め、伺って、私の第一問といたします。
◯市長(郡和子)
ただいまのふるくぼ和子議員の御質問にお答えを申し上げます。
教員の働き方に係る私の考え方と、それからまた、教育環境整備についてお答えをいたします。
子供たちがより質の高い教育を享受するためには、教員一人一人がやりがいを持って職務に専念をし、生き生きとした姿で子供たちと向き合うことが欠かせないものと存じます。
教員の働き方改革に向けましては、教育委員会と各学校において様々な施策に取り組んで、着実に改善が進んでいるところですが、依然として長時間労働の教員が一定数いるなど、さらなる対応が急務と考えています。
このような認識の下、新年度予算案におきましては、これまでの35人以下学級に加えまして、教員が協働して学級担任を担うチーム担任制の導入など、指導体制の充実とともに、学校版BPRなど業務負担の一層の軽減に向けた施策を計上したところでございます。
本市の子供たちへのよりよい教育のための環境整備について、私といたしましても、引き続き教育委員会と共に力を尽くしてまいりたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、教育長から御答弁申し上げます。
◯教育長(天野元)
私からは、教員の働き方の改善について、市長がお答えした以外のお尋ねにお答えいたします。
まず、働き方改革取組指針の目標の達成見込みについてでございます。
年次有給休暇の平均12日以上の取得については、令和4年度は15.1日、5年度は14.7日と、ともに目標を達成しておりますが、教員を個別に見た場合、12日以上取得した者は六四%にとどまっており、一層の取組が必要と考えております。
また、教員1人当たり1か月平均の時間外在校等時間については、令和3年度比で10時間の減少が目標のところ、今年度上半期の時点では約7時間の減少となっており、達成には至っておりませんが、学校現場の工夫もあり、着実に減少しているところでございます。
次に、働き方改革の取組の効果についてでございます。
実効性のある働き方改革の実現のためには、学校現場においてもその意義を理解し主体性を持って改善に取り組むとともに、教育委員会も現場の意見を把握しながら、学校と共に取組を進めることが肝要と考えております。
校務のデジタル化など負担軽減のための新たな取組に際しては、導入初期の段階では変化に対する戸惑いの声などもあることは承知しておりますが、その目的や効果を丁寧に説明しながら、さらなる改善に努めてまいりたいと存じます。
次に、次期働き方改革取組指針における業務の見直しについてでございます。
教職員が児童生徒と向き合うための働き方改革を着実に進めるためには、前例にとらわれることなく、業務の意義や在り方を見直す必要があると考えております。
新年度からの次期取組指針では、コンサルタントに委託して、外部の客観的な目線により業務の改善を行う学校版BPRの実施など、既存の事務事業の点検と負担軽減に向けた見直しを進めてまいりたいと考えており、より実効性の高い働き方改革となるよう取り組んでまいります。
次に、教員の給与体系への認識等についてでございます。
これまで他の指定都市と共に、国に教職調整額の一律支給の見直しを要望してまいりましたが、先般、国からは、教職調整額を段階的に10%まで引き上げる方向性が示されたところでございます。
教員間の公平性や時間外労働を抑制する動機づけの観点などから、教職調整額に関して様々な御意見があることは承知しておりますが、教員の処遇改善に向け、まずは具体的な形が示されたものと受け止めており、引き続き、望ましい制度設計がなされるよう国に要望を続けてまいります。
次に、国の予算案及び本市独自の教員配置についてでございます。
昭和33年の義務教育標準法の制定当時、国においては小学校では一週間当たり24コマが基準とされており、1日平均では4コマでございました。その後、1週間当たりの勤務日数が5日に改められるなど、当時と状況に変化がございますが、令和四年の国の調査では、公立小学校教員の週当たり平均持ち授業時数は、当時と同水準の23.9コマで、これは加配定数の改善などによるものでございます。
今回の国の予算案では、児童生徒の減少により8800人余りの教職員定数の自然減が見込まれる一方、学校の指導運営体制の充実のため、小学校における教科担任制の拡充や中学校における生徒指導担当教師の配置拡充なども併せて示されたところでございます。
今後、国の加配の認定基準などを精査するとともに、引き続き、適切な人員を国に要望してまいります。
次に、条例定数の充足についてでございます。
教員について条例定数との差が大きい理由は、ステーションや中学校の35人以下学級など本市の独自施策部分について、国の加配措置が認められた場合に講師ではなく正規教員を配置できるよう定数を計上していることや、国庫負担の取扱い上、講師を育休代替職員としてきたことが影響しております。
このうち、育休代替職員の扱いについて改善を国へ要望してきたところ、先般、政令が改正され、正職員での代替が可能となりました。これを受け、令和八年度以降の採用者数への反映などを検討しているところであり、条例定数の充足に向けて努めてまいりたいと存じます。
次に、特別支援学級の教員定数についてでございます。
特別支援学級の定数改善につきましては、本市としても重要であると認識し、国に対して学級編制基準の見直しを要望するとともに、併せて、指導体制の改善のために市の予算により指導支援講師や支援員を増員しながら、指導が困難になると見込まれる特別支援学級に配置してきているところでございます。
市独自に定数を見直し、6人を1学級とすることにつきましては、教員の確保や人件費の課題等もございますので、今後も国への働きかけを継続してまいりたいと存じます。
次に、スクールカウンセラー等の専門職の常勤化についてでございます。
本市では、令和元年度から全ての市立学校にスクールカウンセラーを週1日配置しているほか、スクールソーシャルワーカーについては、新年度に中学校を拠点校として配置し、中学校区内の小学校も含めた全ての市立学校をカバーする相談支援体制を構築することとしております。
引き続き、専門職による適切な支援につなげてまいりますとともに、これらの専門職の常勤化について、国庫負担の対象として算定するよう、国に対して要望してまいりたいと存じます。
最後に、養護教諭と学校事務職員の配置についてでございます。
養護教諭及び学校事務職員は、いわゆる義務標準法の規定に基づき、小中学校は各校1名の配置を基本としつつ、一定数以上の学級数を抱える大規模校など、要件を満たす場合については2名の配置としております。
いずれも国の基準に沿って国費負担で配置することが基本と考えておりますが、教員の働き方改革をさらに進めるためには改善が必要であると認識しており、引き続き、国に対し、複数配置基準の引下げや定数改善について要望してまいりたいと存じます。
◯ふるくぼ和子議員
御答弁どうもありがとうございました。
2点ほどお伺いをしたいと思います。
まず、取組指針の達成状況と新年度の取組についてなんですけれども、御答弁は総じて、教職員の働き方の問題についての課題認識、これは明確だけれども、実際にはなかなか到達もできない、こういう悩みもあるんだということだというふうに受け止めたいと思います。でも、その割にはやっぱり取組の中で切迫感が感じられない。そういう御答弁が続いたというふうに思います。
新年度からその取組指針、目に見える前進をつくっていきたいというふうに思うのであれば、やはり現場からの要望をきちんと聞いて受け止めて双方向で進める、これを貫くということが大事な点であるということ。そして、教職員に意識改革を求めるばかりではなくて、やはり教育委員会のほうで具体的に何をするのかということをしっかりと示すべきだというふうに思います。先ほど答弁の中でコンサルタントに委託をしてというようなこともございましたが、やはりこれはきちんと教育委員会、教育局の責任で、ちゃんと教職員との関係で、何をするかということを示していただく必要があるんじゃないかと思います。
そういう意味で、新年度からの取組では、やっぱり業務そのものを見直す、そして取りやめる、こういうこともちゃんと決断もするんだということをきちっとこの場で表明をいただきたいというふうに思うんですけれども、大事だと思うものですので求めたいと思いますけれども、その点、再度お伺いしたいのが一つ。
もう一つは、具体に人を増やすという点です。定数の問題についてはまた違う場でもいろいろ議論していきたいというふうに思うんですけれども、教員の働き方改革、必要だという認識、本当に今広く社会の共通認識になっていますけれども、現場で働く先生方の思いを伺ったところ、働き方改革の真の目的は、教職員が子供の前に健康で明るくいられ、よい授業を行って、子供たちを成長させたい、こういうことなんだというふうに熱く語っていらっしゃいました。
市長に対して、仙台市らしい教育環境整備についてということで求めましたけれども、やっぱり私、市長は教育環境整備の責任を負っている立場でいらっしゃるのですから、定数条例の定数、これ満たしてちゃんと職員配置をすれば、いろんなことができるはずだというふうに思います。教育長のほうからも、新たに教員配置ができるようになってということで、充足をさせる方向にも動いて喜んでいるというお話もありました。
ですから、35人以下学級を30人、25人に進めていくとか、やっぱり8時間労働を基本にした1日の教員の働き方、1日4コマということで教員を配置する、そういうことについて伺ったわけですから、この教員を増やしてこういうことに取り組もうということを正面から受け止めて、もう一度の御答弁をお願いしたいと思います。
◯教育長(天野元)
2点の再度のお尋ねでございます。
順番逆になりますが、まずは定数のほうの話でございます。
これまで様々、35人以下学級の取組もはじめ、してきたところでございます。新年度には、先ほども御答弁したように、チーム担任制を開始するなど、そうした本市独自の取組もしていきまして、指導体制の充実ということも考えているところでございます。
しかしながら、少人数化を含め、義務教育に要する特に正職員の費用については国の負担の下で行うということが基本であり、これまで定数の算出方法などについても、そのような基本方針で行ってまいったところでございます。
国においても、小学校の教科担任制の充実など加配定数の拡充策を、今、拡充案を示しているところでございますので、引き続き、そうした指導体制の充実のための必要な人員の措置について、国にさらに強く求めてまいりたいというふうに考えております。
また、一点目に再度御質問がありました働き方改革の取組指針についてでございます。
切迫感というお話がありましたが、我々も大変この点については切迫感を持っているところでございます。というのも、やはり子供たちに向き合う教員の方々が健康な状況で向き合うということが何よりも大事だというふうに考えております。その意味では、教育委員会、教育局と学校現場の信頼関係ということが何よりも大事でございますので、私もなるべく学校現場に足を運ぶようにして、教職員の皆さんからの直接の声も伺ってまいりたいというふうに考えておりますが、新年度におきましては、正職員の定数のこととは別に、例えば部活動の地域移行であったり、プールの在り方、水泳授業の在り方についても踏み込むところでございます。それから、例えば録音機能つきの電話の設置とか、そうした様々な取組も新年度には始めることとしておりますので、そうしたことも実は私がこれまで学校現場を歩いたところで声を拾ってきたものでもございますので、引き続きそうした取組は進めながら、現場と信頼関係に基づいた働き方改革というのを進めてまいりたいというふうに存じます。
◯ふるくぼ和子議員
重ねて確認をぜひさせていただきたいんですけれども、教員の働き方改革を進めたいという思いは、今の教育長の言葉からにじみ出てきているというふうには受け止めていきたいと思いますし、お話にあったようにいろいろな取組を行って、業務のいろいろな見直しなどもやってきたということを理解はしているんですけれども、それらが実際に抜本的な改善になっていないのではないかということも、一問目で指摘をさせていただいたところです。
その上で具体的に出させていただいたのは、例として挙げたのが標準学力検査や子ども体験プラザというようなことだったわけなんですけれども、やはり全児童生徒にこうした形でやらなくちゃいけない業務というのが、前後の準備も含めて相当な負担、大きな負担、現場の負担になっているということが実際に現場からも出ている声としてあるわけですから、やっぱりちゃんとその声に応えて、この業務、じゃあちゃんと見直そうねとかやめようねと決断するということが求められているのではないかというふうに思うんですね。
ですから、そうした業務、今例に挙げたような業務も含めて、働き方改革のためにはそうしたことも検討をするんだと、対象になるんだと、検討対象になるんだということなのかどうかということを再度確認をさせていただきたいと思います。
◯教育長(天野元)
働き方改革についての再々度のお尋ねにお答えいたします。
特に、悉皆でやっている授業ということでございます。例えば、先ほど御例示しましたプールの水泳授業なども悉皆でございます。そうしたものも、その悉皆授業の存廃、やるかやらないかという白黒だけではなく、例えばプールの授業のように民間事業者の力を借りたらいいんじゃないかとか、そういうこともありますので、悉皆の授業全般にわたっても、私としては新たな目で見詰め直して、様々な手法を使いながら改善、働き方改革につながるよう、働き方改革につながった上で子供たちにしっかりと向き合えるように取り組んでまいりたいというふうに存じます。