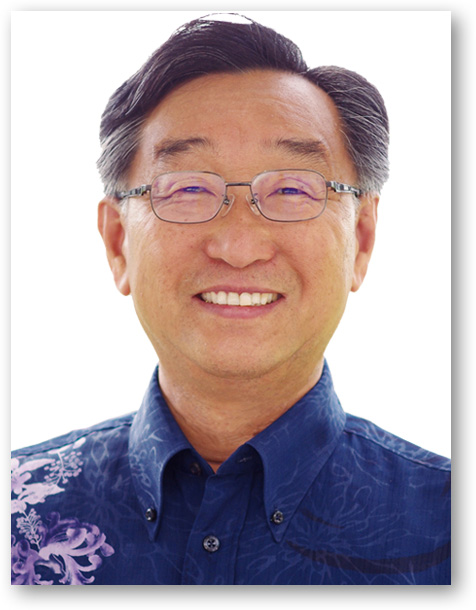質疑・答弁を動画で視聴できます。
今議会から、仙台市議会のYouTubeチャンネルでもご覧になれます。
【概要】すべての地域で生活に必要な地域公共交通を
〇「地域公共交通計画」の進捗と課題
〇「既存の公共交通の補完手段」ではない地域公共交通
〇すべての地域を対象に、実情のニーズの把握を行政主導で
〇路線バスの運賃値上げ、路線・便数の削減をやめよ
〇地域公共交通に活かせる「自動運転実証実験」に
◯花木則彰議員
日本共産党仙台市議団の花木則彰です。地域公共交通について、一問一答方式で質問します。
仙台市地域公共交通計画の取組について伺うとともに、来年度までの計画ですから、これからの方策についても議論したいと思います。
地域公共交通計画には目標値が定められています。地域交通の維持、確保、充実について、現時点での達成状況とそれを踏まえた全体の課題認識について伺います。
既存の路線バスでは、市バスや民間交通事業者でも、便数、路線の削減や運賃の値上げがさらに進む事態となっています。今年4月の市バスダイヤ改正では、夜の便を中心に減らされ、少し残業が延びたりすると終バスに間に合わない路線が増えました。これでは、朝の通勤からバス利用ではなくマイカー利用にせざるを得ません。また、来年に行われるバス運賃の値上げは全体で7%程度の予定が一五%は必要だとされ、遠いところほど大幅な運賃の値上げになり、さらなるバス離れが心配されます。
市民には、路線バスについて一体どうなるのかと不安が渦巻いています。計画でいう利便性の向上による持続可能な公共交通のサービス確保とは逆行する事態だと思いますが、市長の御認識を伺います。
計画には、市民との協働により、地域の実情に合った、誰もが利用しやすく質の高い公共交通を持続的に確保し、自由に移動ができる生活の実現とまちなかのにぎわい向上を目指しますと記されています。どの地域でも、その実情に合わせて、通勤通学はもちろん、買物や通院、金融機関や役所、市民センターなどでの社会活動を含む生活が送れるよう公共交通をつくると考えてよいのか伺います。
また、地域の実情とありますが、市民が主体となって地域公共交通を立ち上げ運用する力を持つ地域も、そこまでは困難な地域もあります。市民協働ができる地域だけを対象とするわけではないと思いますが、併せて伺います。
郡市長は、地域公共交通と地域交通、この2つの言葉をどう定義され、使い分けているのでしょうか、伺います。どちらが広い概念だと考えているかもお答えください。
先日、会派視察で伺った横浜市は、この四月に横浜市地域公共交通計画を策定しました。そこでは、地域交通のうち、既存の公共交通であるバス、タクシーが中心的役割を果たしながら、地域で常に提供されていて、不特定多数の人が安全・安心に利用できる交通サービスを地域公共交通とし、位置づけますと記されています。
地域交通のほうが広い概念であり、マイカーや自分の自転車など利用者が特定される交通も含まれます。そのうち、誰でも利用できる交通サービスを地域公共交通といい、これまでのバスやタクシーに加えて、乗合タクシーや自転車のシェアなどを含めた新しい地域公共交通とされているわけです。求められているのは地域の新しい公共交通なのです。
仙台市が、いまだに地域交通を、既存の公共交通を補完する交通手段、地域が主体となって運行するものと定義していることが計画自体を時代遅れにしていると考えますが、いかがでしょうか。
国のDX推進の分野として自動運転導入への取組が推奨されており、本市においても東北大学と協働しての自動運転バス導入の実証実験が進められています。この取組の目的について伺います。
以上を伺って総括質問とし、残余は一問一答で行います。よろしくお願いします。
◯市長(郡和子)
ただいまの花木則彰議員の御質問にお答えを申し上げます。
路線バスの利便性向上による持続可能な公共交通の確保についてでございます。
これまで本市では、令和三年度末に策定いたしました地域公共交通計画に基づき、路線バスの利便性向上に向けた複数事業者間のダイヤ調整や都心循環線の新設、さらには、新たな通学定期券、せんだいバスFREE+の導入などにより、利用促進に取り組んできたところでございます。
路線バスを取り巻く環境は、利用者の減少、また燃料価格の高騰、それから深刻な運転士不足など大変厳しい状況が続き、減便や値上げが行われてきたものと認識しておりますが、系統の見直しやフィーダー化などの運行効率化や、さらなる利便性向上を図り、持続可能な公共交通の確保に取り組んでまいりたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、関係の局長から御答弁申し上げます。
◯まちづくり政策局長(筒井幸子)
私からは、自動運転の実証実験の目的についてお答えを申し上げます。
本市におきましても、路線バス等の乗務員不足や観光施設までの二次交通確保などの課題を抱えており、自動運転はこれに対応する有効な手段の一つと認識をしております。
将来的に無人での自動運転を行うことを目指し、現時点では、緊急時に運転士が介入するレベル2による実証に取り組んでいるところでございます。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
私からは、地域公共交通に関する御質問のうち、市長がお答えした以外の質問にお答えいたします。
まず初めに、地域交通に係る目標の達成状況と計画全体の課題認識についてでございます。
本市の地域公共交通計画における地域交通の令和6年度末時点の達成状況としましては、意見交換実施地区数が目標15地区に対して13地区、導入地区数が目標十地区に対して9地区、利用者数が目標値1万9710人に対して1万9311人であり、令和8年度末に向けて着実に進んでございます。
計画全体の課題認識としましては、特に路線バスにおいて、利用者の減少や運転士不足に起因する減便、運賃の見直しなどが行われている中、利用者の利便性確保と併せた効率的な公共交通の構築が課題と認識してございます。
次に、地域の実情を踏まえた公共交通に対する考え方についてでございます。
本市では、誰もが利用しやすく、自由に移動ができる公共交通の実現には、比較的大きな輸送需要に適した路線バスと地域の多様な移動需要に適した地域交通などとの適切な役割分担が必要と考えております。
このため、地域公共交通計画では、路線バスの運行状況や沿線人口密度などを踏まえ、主に路線バスによる運行を維持する、みんなで支える路線バスエリアと、地域の方々と共に地域の実情に適した移動手段を検討する、みんなで育む多様な交通確保エリアを設定し、様々な移動手段を組み合わせながら持続可能な公共交通ネットワークの構築に取り組むこととしております。
次に、地域公共交通と地域交通の定義等についてでございます。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律では、地域住民の日常生活や来訪する方の交通手段として利用される公共交通機関を地域公共交通と定義しております。
これに基づく本市の地域公共交通計画では、公共交通を、誰もが利用でき、多数の人を効率的に輸送できる生活に欠かせない交通手段とし、地下鉄、路線バス、地域交通、タクシーなどを対象としてございます。このうち、地下鉄や路線バスを補完し、地域主体で運行する乗合タクシー等を地域交通として、各地域の実情に応じた地域交通の導入に当たりましては、地域に精通した方々が中心となって対応することで持続可能な移動手段の確保につながるものと考えております。
◯花木則彰議員
御答弁ありがとうございました。
地域公共交通計画の目指す仙台市のまちの姿、市民の切実な移動のニーズ、公共交通への要望に応える方策が定まっていないと感じます。何より、地域公共交通、これについての本市の定義がほかの国で言っているものと食い違っているということについてはちょっと驚きました。
全ての地域、全ての市民の生活の足として地域公共交通を確保するという気概が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
本市では、交通政策の一環として、地下鉄やバス、地域交通、タクシーなどの様々な交通手段を組み合わせ、誰もが自由に移動できる公共交通ネットワークの構築を目標としており、その実現に向けて、学識経験者や交通事業者と議論を重ねながら各般の施策に取り組んでいるところでございます。
公共交通を取り巻く環境は大変厳しい状況にありますが、引き続き、関係者と共に知恵を絞りながら、市民の移動手段の確保に取り組んでまいりたいと存じます。
◯花木則彰議員
何のための地域公共交通計画なのかというのはやっぱりはっきりさせていく必要があると思います。
とにかく、仙台市の場合、エリア分けが雑だと思います。路線バスが充実しているエリアをみんなで支える路線バスエリアとし、路線バスなどが十分でないエリアをみんなで育む多様な交通確保エリアとする二択しかありません。なぜこの二区分しかしなかったのか伺います。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
本市における公共交通ネットワークを構築する上では、きめ細やかな路線バスネットワークを有効活用して維持していくことが大切と考えておりまして、一定以上の運行頻度などがあるエリアをみんなで支える路線バスエリアとしてございます。
一方で、これ以外の路線バス沿線の地域に関しましては、みんなで育む多様な交通確保エリアとし、路線バスも含め、それぞれ地域の実情に応じた交通手段の確保に向け、地域の皆様と検討するエリアとしたところでございます。
◯花木則彰議員
みんなで育てる地域交通乗り乗り事業については、補助率が拡充をされ前進していると思いますが、市が勝手にこの2つしか分けていないわけですけれども、エリア分けに合わせて、それに合わないところは要望を出しても冷たい対応です。地域の実情をもっと聞いて、地域公共交通の在り方を一緒に考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
地域交通の検討に当たりましては、みんなで育む多様な交通確保エリア、これを基本として進めてはおりますが、みんなで支える路線バスエリアにおきましても、移動に関する御相談をいただいている地域もございます。
そのような地域からの御相談に対しましては、路線バスとの適切な役割分担に留意しながら、地域の皆さんと意見交換や、本市職員のほか専門家を交え、地域の実情に応じた移動支援の在り方の検討を行っているところでございます。
◯花木則彰議員
そういう要望が出たところには勉強会は開いているということですが、その勉強会で結局断っているのじゃないでしょうか。
若林区のある地域では、ここの地域は乗り乗り事業の対象にはならないと、市バスのルート変更の要望を出してと言われたと聞きました。エリアの分け方が雑過ぎる表れだと思いますが、いかがでしょうか。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
意見交換をした結果として、今ある路線バスを有効的に活用するという結果になる場所もございます。
今、エリア分けはしてございますが、当然、路線バスエリアのはざまという地域もございますので、そこはきちんと意見交換をしながら、どういった移動手段が適切なのかと。路線バスをうまく活用していくという結果もございますし、あるいは地域交通という方向に行く場合もございますので、そこは地域の実情に合わせて検討しているところでございます。
◯花木則彰議員
結局、路線バスということになると、それは市の交通局に言ってくださいと。市の交通局は、それに応えられません、赤字ですからという話になってしまっているわけです。
移動のニーズ、公共交通への住民の要望について中心部へのアクセスのみと捉えているから、こういったエリア分けになっているんじゃないでしょうか。路線バスにおいても、都心、副都心への移動ニーズだけではありません。路線はみんな都心、仙台駅や泉中央、長町に向かって走ります。
しかし、地域の中のスーパーに買物に行くこと、かかりつけのお医者さんに行くこと、小学校、中学校にバスで行くことができない地域があります。生活のための交通ニーズに応えることがなくては、みんなで利用することができないということです。
多様な交通確保エリアにおいても、バス路線への接続により都心アクセスを確保するだけでなく、その地域で生活するための交通ニーズに応える必要があります。地域の実情とこれらのニーズをきちんと調査、分析して、計画を進化させる必要があると考えますが、いかがでしょうか。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
これまでの地域の移動ニーズにつきましては、多様な交通確保エリアでは、移動手段の検討に当たり、地域との意見交換やワークショップなどを通じましてしっかりと把握して取り組んでまいりました。
また、路線バスエリアにおきましても、相談や要望があった場合には、意見交換会等を通じて地域の交通課題や移動ニーズの把握に努めてきたところでございます。
◯花木則彰議員
結局、相談や要望があったところだけなんですよね。
横浜市に行ってきましたけれども、地域公共交通への取組の姿勢が大きく変わったと市民から歓迎されています。まず、駅から八百メートル、バス停から三百メートル以上離れた公共交通圏域外の地域を市が調査しました。その地域に対して、行政主導により、潜在的な移動ニーズの確認とニーズに応じた地域公共交通の導入を支援していくこと、導入に当たって地域の実態を把握していくことをうたっています。区に担当者も配置し、地域への働きかけも進みました。
仙台市では、地域主体と強調するあまり、行政の主導性が弱いのではないでしょうか。市の全域で、移動実態調査、潜在的な移動のニーズの調査を行うこと、区、総合支所に地域公共交通担当を置くことを求めます。お答えください。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
これまでの地域交通を導入してきた地区におきましては、本市が主体となって移動実態調査を実施した上で、地域の方々と意見交換を行いながら導入に向けて取り組んできたところでございまして、今後も、検討段階や導入に際しましては、本市が積極的に地域の課題やニーズの把握に関わってまいりたいと考えてございます。
公共交通の検討に際しましては、全市的な視点も必要でございますことから、現在の体制の下、区と緊密に連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えてございます。
◯花木則彰議員
声を拾うだけでは、市は受け身だし、潜在的ニーズを捉えることができません。区の全域で地域公共交通をつくるという目的を持って仕事をする人が必要だと思います。
地域公共交通の中心的役割を果たさなければならない路線バス、一体どうするのかについて伺います。
効率性を掲げているのはなぜなんでしょうか。これだけ燃料も人件費も上がっていく中で、何が効率性なのか。公共性こそ市が大切にして、必要な支援をしなければならない、そういった瞬間だと思います。路線、便数削減、運賃値上げにストップをかけるべきです。伺います。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
路線バスを取り巻く環境は、利用者の減少あるいは燃料価格の高騰、そして深刻な運転士不足などによりまして、厳しい状況が続いております。
このような状況下におきまして公共交通を維持していくためには、系統の見直しやさらなるフィーダー化による運行の効率化など、バス事業者の経営の安定化に資するような取組が必要だというふうに考えてございます。
本市といたしましても、持続的な公共交通サービスの確保に向け、国の補助金の活用などさらなる支援について検討してまいりたいと考えてございます。
◯花木則彰議員
結局、今やっていることで本当に路線バス維持できるんだろうかと、誰も確信を持てないんだと思うんですよね。
公共性を守るための支援をすべきだと思います。運転士が不足しているのも賃金が低いからですよ。路線の削減とか運賃値上げ、これはますますひどくなるわけですから、これはやめるべきです。もう一度伺います。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
先ほど言いましたように、公共交通を支えている、特に路線バスにつきましては、やっぱり経営的な観点というのは十分必要だというふうに考えてございます。それに対しましてやはり効率化を突き詰めていくと。これから運転士も少ない中でやっていかなければいけないというところもございますし、また、市民の生活のスタイルが変わっていく中で、どういった行動をこれから取っていくのかというところもしっかり調査した上でやっていかなければならないということもありますので、そういった中で、経営的な観点の中で行われる減便ですとか値上げというところは一定程度やむを得ないと思いますが、我々としては、そういった中におきましても、公共交通としてどう維持して守っていくのかというところを今後も突き詰めていきたいというふうに考えてございます。
◯花木則彰議員
突き詰めた方針になっていないんだと思うんですよ。多様な地域公共交通をあらゆる地域に実現させて、幹線路線のお客を増やす、マイカーから公共交通への移行を進める、そういう立場に立つべきではないでしょうか、伺います。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
本市では、地下鉄や路線バス等に加えて、既存公共交通を補完する手段として地域交通を導入し、持続可能な公共交通ネットワークを構築することで、過度に自家用車に依存しない交通体系の実現を目指しているところでございます。
◯花木則彰議員
それでは、結局路線バスも維持できなくなるんじゃないでしょうか。路線バスを利用したくてもできない地域、これをなくして、公共交通への移行を進めてこそ、路線バス、支えられると思います。
計画には運賃施策による公共交通利用の促進の項目があります。主に乗換運賃割引を想定しているようです。それはいいことだと思いますが、それだけで公共交通への移行が進むとは思えません。大胆な運賃政策が求められています。バス運賃の距離制をやめ、一律運賃化する。バス事業者には運行経費に運賃収入が満たない分の補填をする制度をつくる。こういった必要があるんじゃないでしょうか、伺います。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
路線バスの運賃につきましては、分かりやすい運賃体系の導入が市民の利便性向上のために重要であるものと認識しておりまして、例えば本市の都心部では均一運賃として120円パッ区を導入しているところでございます。
本市では、長大路線を抱えておりますため、全市一律の運賃は難しい面もございますが、今後の路線再編等を見据えながら、運賃制度や支援の在り方につきましても交通事業者と意見交換を行ってまいりたいと考えてございます。
◯花木則彰議員
また、多様な交通確保エリアについては、地域公共交通を原則無料にして、幹線バスに接続することで、マイカー利用から公共交通利用へと移行を図ることを提案をしますが、いかがでしょうか。地域内での買物や通院などが気軽にできるため、地域内循環経済でスーパーや病院の撤退も防げるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
地域交通の無料化は、公平性の観点などから課題が多く、困難と考えてございます。
地域交通の料金設定につきましては、近接する路線バスやタクシーなどとのバランスに留意し、一定の補助の下で利用しやすい料金を設定しているところでございます。
◯花木則彰議員
公共交通は都市のインフラだと市長も認めておられます。例えば、道路には維持費だけで年間百億円近くの予算をかけています。地域公共交通にその何割程度かをかける決断を市長が行って、どの地域でも安心して暮らし続けられる仙台市としてまちづくりを進めることを求めますが、いかがでしょうか。
◯都市整備局長(反畑勇樹)
公共交通は市民生活に欠かせない社会インフラの一つというふうに認識しておりまして、これまでも、市交通局への一般財源からの繰り出しやせんだいバスFREE+の導入、また地域交通の運行支援などに取り組んできたところでございます。
引き続き、さらなる利便性向上による利用促進や、フィーダー化などによる運行効率化に加えまして、交通事業者への支援の在り方も検討するなど、市民の皆様が安心して移動できる持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け取り組んでまいりたいと存じます。
◯花木則彰議員
どのぐらいの規模でちゃんと予算もかけるのかということが大事だと思います。
茨城県境町に行ってまいりました。2020年11月に全国初の自動運転バスの定期運行が始められ、現在では、3ルート、22のバス停を1日33便、平日はもちろん、日曜、祝日も毎日運行しています。運賃はゼロです。町民以外の方も無料で利用できます。レベル二で、オペレーターは同乗しています。時速二十キロ未満ですが、実際乗ってみると結構速く感じます。大きな道路、車の交通量やスピードが速いところには向きませんが、スロースピードから始めれば、バスが減らされている郊外の住宅団地や農村部の地域公共交通には十分使えそうだと感じてきました。仙台市での実証運転は地域公共交通を想定したものにもすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
◯まちづくり政策局長(筒井幸子)
自動運転は、交通事業者で深刻化する運転士不足の課題解決を通じ、地域の足の確保にも寄与するものと認識をしております。
現在は青葉山エリアにおいて技術実証に取り組んでいるところでございますが、今後の実証に当たっては、地域公共交通確保の観点も踏まえ、ルートや車両等の選定などを進めてまいりたいと存じます。
◯花木則彰議員
境町では、自動運転バスと、あと、中心部だけなんですけれどもね、それ以外の地域はオンデマンドバス、これをどちらも無料で利用できるようにして、町内全域での地域公共交通ができたことで、高速バスへの接続が可能になった。屋内遊び場キッズハウスさかいにこどもたちだけで行くことができる安心なまちになった。夫が車で仕事に出かけていて、日中車が使えない子育て中の母親が、様々な子育て支援策に参加でき、喜ばれています。もちろん高齢者の通院、買物も便利になり、バスの中が住民同士のコミュニケーションの場になっているとお聞きしました。
こういった、やはり地域公共交通を実現するというために資する自動運転にしなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
◯まちづくり政策局長(筒井幸子)
自動運転の実装に当たっては、技術面や経営面の課題をクリアしていくことに加えまして、市民の皆様の理解を得ていくことも重要であると認識をしております。
これまでの実証におきましても、実際に1000人近くの方に御乗車をいただき、御意見をいただいているところでございますけれども、引き続き、自動運転が市民生活に寄与していくものとなっていくように、試乗の機会等も通じて、丁寧に市民の皆様にもその効果をお伝えし、様々な意見をまたお聞きしていきたいというふうに考えております。
◯花木則彰議員
地域公共交通計画で描く仙台市の未来像が、広い仙台市の全ての地域で地域公共交通を実現して、都心へのアクセスとともに、地域内での生活を送ることができる、住民が幸せに暮らし続けられる都市になってこそ、市民から選ばれるまちになるんだと思います。
まちの中心部再開発や機能集約型といって周辺地域を切り捨てる政策を改めるつもりはありませんでしょうか、市長にお聞きいたします。
◯市長(郡和子)
これまでも本市は、持続的な公共交通の維持に向けて取り組んできています。利便性の向上ですとか利用の促進、それからまた経営の安定化を図っていくということも考えつつ、自動運転など新たな技術の導入についても御承知のように取り組んでいるところでございます。
仙台市は大変広い面積を持っておりまして、それぞれで課題は違っていると思いますけれども、交通というのは、どの住民にとっても、市民の皆様方にとっても関心が高いものですし、本市といたしましても、重要な取組だというふうに認識をした上で、これまでも取組を進めているところというふうに考えています。
今後も、地下鉄、路線バス、地域交通はもとより、新たなモビリティーといった多様な交通手段、これらを適切に役割分担をしながら有機的につないでいくということで、市民の皆様方お一人お一人がそれぞれの実情に応じて快適に移動できる、そうした生活の実現に結びつくように取り組んでまいりたいと考えております。
◯花木則彰議員
結局、これまでの取組では路線バスを維持するという展望が出てきていないんですよね。ここにやはり答えを出していくような取組を仙台市が行う必要があると。その鍵は、やはり地域、それぞれの地域の中で生活できる、そういった公共交通をつくるということではないかと私は思います。
今後もこうした全ての地域での地域公共交通の実現を目指して取り組むことを表明して、質問を終わります。