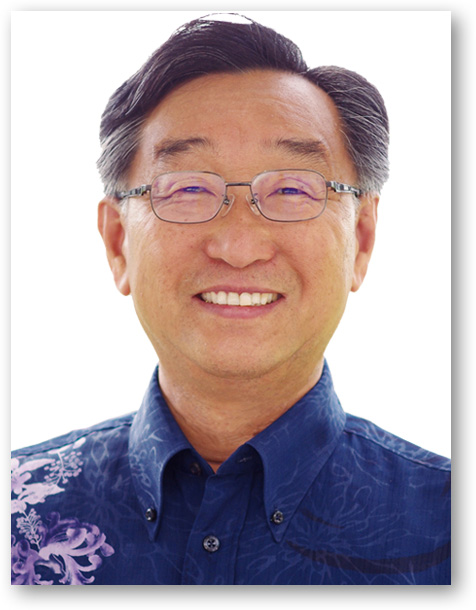質問・答弁を動画で視聴できます。
今議会から、仙台市議会のYouTubeチャンネルでもご覧になれます。
【概要】市民の命と暮らしを守る土台である農業・漁業を支える施策を
〇大震災時に支援を受けた農業機械の更新への補助を
〇農地環境維持に市の役割と責任の発揮を
〇新規就農者への支援強化は急務
〇学校給食への環境保全米のさらなる活用を
〇フードバンク、子ども食堂への支援を早急に
〇記録的不漁、資材高騰で苦境の農業に支援の抜本的強化を
〇少なすぎる農業・漁業予算、いまこそ拡充を
〇吉田ごう議員
日本共産党仙台市議団の吉田ごうです。市民の命と暮らしを守る土台である農業、漁業を支える施策について一般質問いたします。
昨年から始まった令和の米騒動は、米の価格高騰が家計を圧迫し、長引く物価高騰に苦しむ市民の方々をさらなる苦境に追い込んでいます。食べ盛りのこどもにお代わりをさせてあげられないと、シングル世帯など生活困窮にあえぐ市民の方々からの悲鳴が上がっています。市長は、この米価格高騰により、市民生活にどのような影響があるとお考えでしょうか、伺います。
米価格がこれほど高騰した要因は、2023年産米が高温障害などから需要より44万トンも不足したことにあります。若林区のある農事組合法人からは、田植を終えたばかりなのに、早くも卸業者や大手スーパーが来て、米の確保を予約したいとの要請があり、文字どおり青田買いが過熱している、と驚きの声が寄せられました。
こうした米不足が起きてしまう原因は、政府が、米価は市場が決めるとして価格保障しなかったこと、米農家に減反を押しつけ、支援を縮小し、米の生産を衰退させてきたことなど、これまでの農政の失敗にあることは明らかです。
全国的に米農家は、2000年以降、175万戸から53万戸と3分の1へ激減、米の生産量も約3割減るという異常事態が続いています。本市の水稲収穫量は、2000年から2023年の間に約1万トン減少し、作付面積は約半分になりました。食料自給率は、一昨年試算値で、カロリーベースで僅か5%、生産額ベースでは4%という水準です。市民の命と暮らしを守る基盤である農業生産を抜本的に増やす施策が緊急に求められておりますけれども、市長は、これまでの本市の農政について総括をどのようにされているのか。また、本市の農業政策について、今後どのようなビジョンをお持ちであるのか、お答えください。
米農家の方々からは、ビニールや農薬等の資材は軒並み2から3倍に上がるなど、ありとあらゆる経費が高騰し、依然として経営が苦しいという悲鳴が上がっています。農家さんからは、一時的に米価格が上がったとしても退職金のようなものだ、と営農継続に展望が持てずに離農せざるを得ないとの声も相次いでいます。
この間、若林区の農事組合法人や機械利用組合の方々からお話を伺ってきました。震災後の支援で手にした農業機械が更新の時期に差しかかっている。津波被災地では大きな石がごろごろと出てきて、トラクターの刃の摩耗などダメージを受ける状況の下、1000万円超かかる修理費も何とか捻出し大事に使ってきたが、老朽化で限界が近い。何台もある機械が一斉に更新の時期を迎えるため、出費が大変、という声が寄せられました。
本市は、昨年度から集落営農組織等へスマート農業機械の補助を開始しましたが、補助対象経費10分の3以内という現在の補助率をもっと引き上げるべきだという声や、これまで使ってきた農業機械を更新する際にも使える補助が欲しいとの声をお聞きしています。こうした支援制度の充実が必要と考えますが、いかがでしょうか、伺います。
農地の環境保全をめぐる課題についてです。
荒浜地区の農事組合法人からは、県道塩釜亘理線の下道、約四キロに沿って、幅約2メートル、深さは約1.5mの大型排水路があり、水路のり面の草取りや底に堆積した土砂の撤去等の作業は、土地改良区や耕作者が取り組んでいる。荒浜は大震災後に災害危険区域指定で居住者がいなくなり、作業は農業者のみで担っているが、地域に2つある法人のメンバーでは人手が足りない、との声が寄せられました。東部復興道路の荒浜交差点には「歩行者や自転車は下の道を通って」との看板もあるにもかかわらず、水路のり面から茂る雑草が歩道を塞ぐ事態も出ています。また、この大型排水路は、農業用以外にも様々な用途で使われており、地域の農業者に日常的な管理の責任を負わせている実態を解消しなければなりません。現地を確認し、農業者と共に対策を検討すべきではないでしょうか、伺います。
同様に、各地で農業者や地域住民などの担い手不足による農道や水路の維持作業の困難や、今後に不安の声が寄せられています。市議と農業委員の懇談会でも、地域での草刈りに人が集まらない状態で、補助を上げて外部に発注するなどの検討も必要との意見がありました。現場の実態をよく聞き、外部発注や多面的機能支払交付金に市が独自に上乗せするなど、様々な支援が必要と考えますが、いかがでしょうか。
本市の農家数は、2005年の4627人から、2020年には2521人と右肩下がりを続け、基幹的農業従事者の高齢化率は2020年で70.9%に上っており、新規就農者対策の拡充は待ったなしです。しかし、国による新規就農者への支援金が切れた後に、営農の継続に困難を感じ、将来の展望が持ちにくいなどの理由から離農するケースが多いことも課題です。二本松市では、受入れ農家への支援はもちろん、就農希望者にも研修期間中の家賃や生活費の補助を行っています。また、新潟市では、にいがたアグリベース事業として、国の事業の要件に合わない場合も市が百万円を補助する親元等就農支援金制度や、劣化したパイプハウスなど既存施設の修繕に係る費用の助成などを市独自で行っております。さらに就農希望者の様々な相談に応じるワンストップ窓口も設置するなど、新潟市を農業を始める拠点として選んでもらうための努力を行っています。農業機械や運搬に使うトラックを運転するための免許取得費用への支援制度も必要です。各地の事例に倣い、本腰を入れた新規就農支援策を講じるべきと考えますが、いかがでしょうか、伺います。
農業に関心を持つ市民を対象に、研修後、市内農家のもとで農業を手伝う農業サポーター制度が、担い手不足に悩む多くの農家から歓迎されています。サポーター養成講座のせんだい農楽校は、定員が16名のところ、今年度は34名応募し、倍率は二・一倍に上りました。農家と市民から多くの期待が集まる制度であることから、応募した方を全員受け入れるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
農産物の地産地消や食材の有機化、また、学校給食への活用や無償化などで、持続可能な農業とともに地域活性化にもつながるアグロエコロジーが、全国各地で推進されています。
まず、学校給食への市内産米の活用について伺います。
本市は2021年度から仙台農協と連携して環境保全米を市立学校で提供していますが、週3回米飯を100%にするために必要な820トンに対し、昨年度は675トンと供給率76%、供給期間は7か月見込みと、まだまだ足りません。本市は、学校給食向け環境保全米の生産者に60キロ当たり250円を上限とする補助を行っていますが、農業資材の高騰による米生産の困難からも、少な過ぎる補助金の増額を早急にすべきと考えますが、いかがでしょうか。
東京都日野市では学校給食に地元農産物を活用する取組を行っています。学校や農家、JAなどが供給量と価格を調整する相談を行い、契約栽培事業奨励金が農家に交付されます。市場価格より高値で出荷できることで農家から大変喜ばれ、保護者やこどもたちからは安全でおいしい地元農産物がとても喜ばれています。地産地消の推進で生産者と消費者を結びつけることにより、農業振興や地域活性化、そして、こどもたちに安全でおいしい農産物を届ける取組を、ぜひ本市でも始めようではありませんか、伺います。
本市では、市内農家による旬の香り市、また、11月を、とれたて仙台地産地消月間として、とれたて仙台フェアやせんだい収穫まつりが開催され、市民から親しまれています。米と農業の大切さを改めて痛感する今年の秋、例えば、仙台産米の産直販売や環境保全米についての周知啓発、米生産について学ぶ催しなどを行う取組が、ますます重要であると考えます。本市の米農家と消費者をつなぐ取組を各地で行うなど、さらに強化させ発展すべきと考えますが、いかがでしょうか。
困窮者支援の現場でも米価格高騰は深刻な課題です。NPO法人フードバンク仙台の理事の方からお話を伺いました。2023年度に約5000人から寄せられた食料支援依頼が、2024年度には延べ約7100人と大幅増に、あわせて食料支援量も昨年度は前年度比196%とほぼ倍となり、同法人が創立して以降、過去最多の依頼件数及び食料支援量に上ったとのことでした。
食料支援の依頼をされた生活困窮者の方々は、一日一食でしのいだり、中には一週間以上満足に食べることができなかったなど飢餓状態に追い込まれたり、生命に関わる切迫した事態となるケースもあるとのことです。御当局は、生存権が脅かされているとも言うべき生活困窮者の方々についての実態を把握されていますでしょうか。お答えください。
本市のフードバンク活動支援助成金の限度額は、現在、一団体につき上限百万円とのことです。しかし、フードバンク仙台の方々からは、食料依頼件数の激増に対応するために職員を増員するなど運営費用の確保に苦労されているとの声が寄せられています。フードバンク団体の活動を保障するために、緊急に助成限度額を増やすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか、伺います。
本市の漁業と漁業者への支援について伺います。
我が国の漁業経営体は、沿岸、小型漁業者が94%を占め、厳しい規制による自主的な管理で水産資源を守りつつ食生活に欠かせない水産物を提供していることはもちろん、地域経済への貢献など、かけがえのない多面的な役割を発揮しています。定置網漁を営む荒浜地区の漁業者の方からお話を伺ってきました。
これまではアキサケが主力だったが、温暖化など海洋環境の変化からか漁獲量が大幅に減り、以前は何トン単位で捕れたのが、数えられるほどの百匹を切るまで減ってしまった。その分を補填するためにアカガイ漁に取り組んでいるが、こちらも昨年秋に酸欠状態で死滅が多かったことや、魚と違い育つまで時間がかかることから、収入が最盛期の一割以下にまで落ち込んでいる、との切実な訴えでした。
市長はこうした深刻な本市漁業の実態についてどのような認識をお持ちであるのか伺います。
物価高騰の下、漁具の確保や漁船の維持にも困難を抱えています。アカガイを海底から捕獲するためのマンガンという漁具があります。10年前までは一丁当たり10万円ほどのものが、鉄材の高騰で15万円を超えたが、定期的な交換が必要とのことです。
また、定置網に付着したフジツボや海藻などを取り除くための防藻剤も、以前は200リットルドラム缶1本当たり10万円を切っていたものが13万円ほどに、さらに漁船は一年に一度、おかに上げて船底塗料の塗り直しが必要ですが、専門業者に依頼して行う作業で1回につき約70万円もかかるとのことで、漁業に必要な備品や装備への公的支援を求める声が相次いで寄せられています。
また、定置網漁で水揚げした後、多様な魚種ごとに選別する必要があり、石巻市場内の魚問屋がその仕分作業も含めて引き受けることから、水揚げした海産物を保冷タンクに詰め、トラックで石巻まで運搬しています。それに係るガソリン代の負担も大変重いとのことでした。漁具や漁船の維持、運搬に係る経費などへの支援が必要と考えますが、いかがでしょうか、伺います。
本市の漁協に加盟している漁業者数は、内水面の広瀬名取川漁業協同組合が四百名、そして、宮城県漁業協同組合仙台支所は47名で、皆さん、かけがえのない役割を果たしておられます。このうち、県漁協仙台支所の事務所について伺います。
仙台支所は、大震災で深沼にあった事務所を失った後、現在は民有地を借りて、毎月、地代18万円を支払っているとのことです。その財源は組合員の方々が支払う手数料ですが、漁獲量の減少などで苦境の漁業者にとっては手痛い出費であり、組合員の減少からも事務所の維持は大変厳しい状態とのことでした。
事務所は、会議や営業事務に加えて、漁具の作成や補修作業ができるスペースを持ち、本市漁業の活動拠点ともいうべき大切な機能を担っています。本市としてどのような支援ができるのか検討していくために、漁協の方々から実態についての聞き取りを行うべきです。伺います。
本市には豊かな水産資源があるにもかかわらず、御当局の水産業、漁業の位置づけは弱いと、率直に指摘せざるを得ません。経済局の中に水産や漁業と名がつく部署がないことに、漁業者の方々からも悲しみの声が寄せられています。ぜひ水産や漁業を冠する部署をつくるべきと考えますが、いかがでしょうか。お答えください。
新たにつくる部署では、本市漁業の姿を多くの方々に知っていただくために、漁業者と連携しながら仙台産の水産物のブランディング戦略の確立や、中央卸売市場、また、杜の市場などで周知する取組が必要と考えます。漁業者が長年にわたり紡いできた歴史を次世代に引き継いでいくために本気の取組が求められますが、いかがでしょうか。市長に伺います。
本市の農水産業振興費は約2億5000万円ほど、そのうち漁業予算は僅か200万円に満たない額しかありません。米不足、価格高騰で、食料は命の根幹であることを改めて痛感しました。市民生活の基盤である食料生産の拡大に向けて、国・県任せではなく、市独自の取組を進めるための抜本的な予算増が今こそ必要と考えますが、いかがでしょうか。
また、本市は、一大消費地であるとともに、広大な農地と太平洋沿岸の漁場も持つことから、食料の生産力と地産地消を基にした循環型経済に向かう大きなポテンシャルがあります。農業と漁業の持つ多面的機能による経済活性化や都市の魅力向上に一層生かすべきではないでしょうか。
今こそ、食の豊かさを都市の豊かさとしてアピールするときだと考えます。本市農業、漁業の振興に向けた決意を最後に市長に伺って、第一問といたします。
◯市長(郡和子)
ただいまの吉田ごう議員の御質問にお答えを申し上げます。
米価高騰による影響及び農業、漁業の振興についてでございます。
今般の米価高騰は、米の店頭での小売価格が、昨年同月比で2倍近い金額となるなど、家庭はもとより、外食産業や、また、食料品製造業など、幅広く市民生活に影響を及ぼしており、安定的な食料供給がいかに大切か、改めて認識をしたところでございます。
本市のおいしいお米や新鮮な海産物は、インバウンド誘致をはじめ、本市のシティーセールスにおける大きな魅力の一つでもあることから、これを支える農業者、漁業者が安心してなりわいを継続できる環境を整えることが何よりも重要でございます。
そのため、国や県と共に、基盤整備や担い手の確保等、安定的な事業継続に向けた支援に取り組みながら、地元の農水産物の魅力を発信し、需要の拡大に努めてまいります。
こうした取組により、大消費地と産地とが近接している本市の特徴を最大限に生かしながら、本市農業、漁業の振興を図り、食の魅力でも選ばれる都市・仙台を目指してまいりたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、関係の局長から御答弁申し上げます。
◯健康福祉局長(郷湖伸也)
私からは、生活に困窮している方の把握状況についてお答えをいたします。
本市では各区保健福祉センター保護課や仙台市生活自立・仕事相談センターわんすてっぷにおきまして、生活に困窮された方への相談支援を行っております。
その内容といたしましては、昨年度の生活保護開始数が2529件と前年度に比べ298件増加しておりますほか、昨年度、わんすてっぷでお受けした経済的困窮に係る御相談のうち、より深刻と考えられます食糧支援を求める御相談が56件と、前年度を上回っている状況でございます。
今後も、わんすてっぷやフードバンク団体等の関係機関と緊密に連携し支援の充実に努めてまいる考えでございます。
◯環境局長(細井崇久)
フードバンク団体への助成金の増額についての御質問にお答えいたします。
本市が助成金を交付しているフードバンク団体につきましては、未利用食品の確保をはじめとした運営等に係る現況や課題等について毎年訪問の上、意見交換を行っているところでございます。
今後、物価高の影響について、団体にヒアリングを行い、本市と同様にフードバンク団体へ活動助成を行っている県の対応状況を踏まえつつ、追加支援の必要性等について検討してまいりたいと存じます。
◯経済局長(木村賢治朗)
経済局に係る一連の御質問のうち、市長からお答えしたもの以外につきまして御答弁申し上げます。
まず、農政の総括及び農業の今後のビジョンについてでございます。
本市におきましては、全国的な傾向と同様に農業従事者の高齢化が進んでおりまして、その数も減少傾向にございます。
このため、本市では、新規就農者のほか、中核となる認定農業者や集落営農組織等、多様な担い手の育成、確保に努めるとともに、農地の集約化等を進め効率化を図ってきたところでございます。
今後につきましては、スマート農業機械による省力化や高収益作物の導入等、稼げる都市農業を目指し、本市の農業が将来にわたって持続可能なものとなるよう、取組を推進してまいりたいと存じます。
次に、農業機械の補助制度の充実についてでございます。
担い手不足への対応としての省力化や、一層の生産性向上を図る観点から、令和6年度より、スマート農業技術導入を促進する本市独自の補助制度を創設したところでございまして、昨年度は6件、御利用がございました。
スマート農業技術の普及を図るために、まずはこの制度の周知に取り組み、より多くの農業者に御利用いただけるよう進めてまいりたいと存じます。
農地の環境保全をめぐる課題についてでございます。
現在、地域の農業者の皆様には、水路及び農道の除草や土砂の撤去など、国交付金や本市補助金を活用し、農業用施設の維持管理の一部を担っていただいておりますけれども、高齢化や担い手不足等の課題を抱える中、負担が増加してきているものと認識しております。
今後、地域の御要望などを伺い、それぞれの実情や課題を捉えながら、農業者の皆様の負担軽減に向けた方策を検討してまいります。
新規就農支援策についてでございます。
本市の新規就農者の取組といたしましては、JA等関係機関と連携し、国の支援策を活用するほか、就農相談会を実施しております。
令和6年度からは、農業法人等が新規雇用する際の雇用就農支援事業や、農業者が就農希望研修生を受入れ、研修を行う、新規就農希望者研修支援事業を開始したところでございます。
今後とも、就農後の巡回指導など伴走支援を行いながら、新規就農者が営農を継続、定着できるように努めてまいります。
農業サポーター養成講座の増員についてです。
農業サポーター制度は、農繁期等の一時的な人手不足を補完する役割を担っているものと認識しております。
養成講座では約半年間の野菜栽培等の体験学習をいたしますが、そのための農場に限りがあること、また、実際のサポートの要請件数などを考慮いたしまして、現在の定員としているものでございます。
学校給食向け環境保全米についてでございます。
本市では、令和3年度から学校給食向け環境保全米と普通栽培との生産資材の差額の一部を補助してきたところでございます。
加えて、昨年度からは、新設された国の交付金を、環境保全米を栽培する農業者に対して交付しているところでございまして、引き続き、農業者の環境保全米の生産を支援してまいります。
次に、学校給食の地産地消についてでございます。
学校給食を通した地産地消の推進は、生産者にとってやりがいにつながるとともに、こどもたちに農業に関心を持ってもらう食育の観点からも、重要と認識しております。
今年度、教育局と連携し、地元生産者と学校給食担当課、学校給食納入事業者も参加したマッチング商談会を開催したほか、今後、学校栄養士が生産者を訪問する交流会開催等を予定しております。
ここから生まれた生産者と学校給食関係者との結びつきをきっかけに、引き続き、学校給食の地産地消推進を図ってまいります。
次に、米生産者と消費者をつなぐ取組についてでございます。
本市では、米の栽培現場の状況や生産者の声を知っていただくため、SNSによる情報発信を強化しております。
あわせて、とれたて仙台フェアでは、市内生産者の紹介とともに、仙台産金のいぶきのリゾット提供を行うなど、生産者と消費者の顔が見える交流の機会創出に継続的に取り組んできたところでございます。
今後とも、生産地と消費地が近接する本市農業の特徴を生かして、市内産農産物のさらなる消費拡大につなげてまいりたいと存じます。
次に、本市漁業の実態に係る認識、漁具等への支援等についてでございます。
本市漁業を取り巻く状況につきましては、漁協等との意見交換を通じ、海水温の上昇等による影響などを伺っているところでございます。
本市では、漁協または漁業者への直接の支援は実施していないところでございますけれども、県と本市で出捐している基金を通じ、漁協への助成事業は行っております。
引き続き、漁協との連携を密にし、市内漁業者の実情を把握して、適切に対応してまいりたいと存じます。
漁業を冠する部署の創設及び次世代に引き継ぐ取組についてでございます。
組織名称につきましては、主たる所管業務を中心にしておりまして、現行、適切なものと考えております。
本市産の水産物につきましては、供給面で課題がありますが、スポット的にPRを行うなど、その可能性について、次世代に引き継げるように検討してまいりたいと存じます。
最後に、農業、漁業に係る予算についてでございます。
農業、漁業に関する事業は、圃場や漁港等の基盤整備など、国・県のそれぞれのレベルで基幹的な支援が行われているところでございまして、本市におきましては、施設の維持管理や担い手の育成等に取り組んでおり、加えて、六次産業化やSNS等を通じた情報発信、スマート農業機械の導入支援等、重点化した独自の支援策を講じているところであり、まずは、これらの事業の着実な推進に向けて努めてまいりたいと存じます。
◯吉田ごう議員
ご答弁ありがとうございました。
何点かにわたって再質問をさせていただきたいと思います。
農業サポーターについてなんですけれども、農場に限りがあるとか、あと、派遣先の農家との関係で定員増を行わないというお話だったかと思います。
私、若林区井土の農業法人の方からお話を聞いてきました。農繁期も含めてですけれども、非常に人手が足りなくて、農業サポーターによる協力を求めているという声が非常に強く寄せられました。それで、現場の需要をもっと把握することですとか、また、やってみたいという市民の方々、大変多いわけですので、現場の農家さんと農業サポーターをやりたい、やってみたいという市民の方々とのマッチング含めて、もっと強力に推進するべき、実態も把握するべきだと強く思っています。
せんだい農楽校、資料頂きまして、令和5年度から7年度、定員が16名で変わらず。全てね、倍率以上の方々来ているんですね。令和7年度が2.1倍で最もこの直近3年間で高くなっていますので、そういった期待に応えるということで進めていただければと思います。
次に、農業用機械への支援制度についてであります。
御答弁では、スマート農業機械導入への支援制度を始めて、これまでどおりの補助率10分の3でいくというふうに解釈しましたし、そのお知らせを進めていくこと、あと、そのほかの農業機械、従来型の機能のものについては、国の支援事業の紹介とか手続の支援、今までも行っておられましたけれども、その枠を超えないというものであったというふうに思っています。
スマート農業機械導入支援事業、これ大変歓迎されています。労働負荷が減る、熟練しなくても機械が運転できるということなんですけれども、補助率の引上げの要望がたくさん出ています。やっぱりこれだけの資材高騰で農業者の皆さんは苦慮されていますので、10分の3、非常に高額な機械でもありますので、十分の3からの引上げ、これ必要かなと思っています。
あと、従来型機能の農業機械を使っていて、その機械の更新を望む農家も、これももちろん多いですよね。高額であるのでスマート農業機械でなくて、今まで使っていたのと同じタイプのほうがいいと。また、御自身の農業、営農スタイルから、その機能がいいということも声が多く出ております。この間、つくば市では、国や県の補助事業の要件に合致しない農業者に対するつくば市独自の支援策を昨年度より新設をしたとのことです。本市でもせめて補助率の引上げや、従来型機能の農業機械を更新する際の支援制度が必要だと考えます。それについて検討するなどの前向きなお答えがありませんでしたので、再度求めますけれども、いかがでしょうか。
次に、漁具や漁船の維持に係る経費への支援についてです。
御答弁では、海洋環境の変化や資材の高騰、漁業者の皆さんは大変苦境に追い込まれている下で支援の必要性は認識しているんだけれども、国や県の支援策の紹介、また、今後の国の動向などということで、これも枠を出ない御答弁だったということで、非常に残念だと思っています。愛知県蒲郡市では、ロープやマンガンなど漁業用具の購入費補助を行っております。こうした各地の事例に学び、貴重な本市漁業と漁業者を守るために、漁具や漁船に係る経費への支援が必要だと考えますけれども、再度伺いたいと思います。
そのためにも、水産や漁業に関する専門の部署が必要だと考えます。経済局長の御答弁で現行で適切というお話がありましたけれども、漁業者の皆さん、水産関係の皆さん、そう思っていないと思いますよ。やっぱり位置づけが非常に弱いと、自分たちのところ見てくれていないと、こういったやっぱり声がたくさん出ていますので、専門の部署があってこそ、漁業者に実態を聞き、相談する体制をつくるとか、また、支援制度を進めることとか、販路開拓、ブランディング戦略の構築など、具体的に前進をさせることができると考えます。この点についても再度伺いますけれども、いかがでしょうか。お願いいたします。
◯経済局長(木村賢治朗)
再度のお尋ねにお答えいたします。
まず、農業サポーター養成講座でございますけれども、現在修了した方というのが百人を超える方いらっしゃいますけれども、実際にサポーターとして活動できるという方が半数に満たない状態でございます。希望者は多いということでございますが、お話を伺いますと、自分の家庭菜園を楽しむために勉強してみたいという方ですとか、あるいは、やはり実際のサポートの要請とマッチングしない場合が結構あるということでございまして、私どもとして把握しているニーズの範囲といたしましては、現在の16名という程度でいいのではないかというふうに判断しているところでございます。
次に、スマート農業機械の補助制度についてでございます。
実際、スマート農業機械といった場合に、1台がやはり数百万から数千万円というものでございまして、一般の農業者の方が気軽に購入できるものではないというものではございます。実際の補助制度の対象となっている方は、農業法人の方がほとんどという状態でございます。
そうした中で、より一層スマート農業を広げていくというためには、今まで導入していなかったところなどにも入れていただくと、そういった意味で幅広く進めるということを中心にやっていきたいというふうに考えているところでございます。
次に、漁業関係への支援でございますが、宮城県漁協の仙台支所とは何度か意見交換なども担当のほうでさせていただいておりまして、その際に、最近の海の状況というものは承知しておりますけれども、個々の漁業者に対する支援等につきましては、一時期ありました燃料費の話ですとか、そういった時代はありましたけれども、それ以外の部分につきましては、今の時点で御要望というものは特に承ってない状況でございます。
しかしながら、今お話がございましたので、実際、漁業者の方がどういうような御要望をお持ちかということも含めて、いろいろまた情報収集をして考えていきたいというふうに思います。
最後に、組織でございますけれども、実際の問題といたしまして、職員一名に該当する業務量が今の時点ではございません。名称をつけて組織をつくって、それからということでございますけれども、先ほど御紹介がありましたような漁業をされている方の実数と、それから、実際の水揚げの量とか、そういったものを判断したときに、現在対応している人員によって十分であるというふうに考えているところでございます。
◯吉田ごう議員
御答弁ありがとうございます。
再々質問をさせていただきます。
農業サポーター養成のためのせんだい農楽校について伺いますけれども、今のお話だと、家庭菜園等をやるための学びとして農楽校に行って、実際にはサポーターをやる人が半数に満たないので今のままでいいというお話だったのですけれども、これね、農業サポーター養成のせんだい農楽校というのは、市民の方が農業に関心を持ってもらうと、そのためにある取組でもあるんですよ。家庭菜園をやっていただいたり、家庭とか地域で活用していただくために農業の知識を得る、研修を受ける、これすばらしいことだと思いますよ。それの認識の改めとですね、先ほども申しましたけれども、現場の農家からは現場に来てほしいという声が出ていますので、やっぱり、しっかり強化していくということで考えてほしいと強く思います。
あと、漁業者への漁具等、漁船の維持に係る経費の支援ですけれども、燃料対策を行って、しかしながら、今の時点では要望を承っていないと。これは重大な答弁だと強く思います。燃油価格の対策をしたと。では、今どういうことに困っているのか。これだけの資材高騰、海で捕れなくて困っている中で、これもっとね、聞くべきなんじゃないですか。やっぱり現場にもっと出て、要望を聞いて、漁業者の皆さんと共にこの本市漁業を守る取組をやっていくということがどうなのかと、再度求めていきたいと思います。
◯経済局長(木村賢治朗)
農業サポーター養成講座ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、実際に農業をやっている方の一時的な人員不足等の農繁期とかに支援をするという本来の目的もありますので、それとのバランスということで申し上げました。
もちろん、もっと拡大して、深く農業に親しみたいという人に対して間口を広げるべきというお話でございますけれども、現状といたしまして、実際に使える実習できる農地に限りがあるということもございまして、もとはもうちょっと人数多かったんですが、実際、土を触れない人が出てきていたのでこの人数まで絞ったという経緯もございます。そういった中でございますので、今後、その状況等をよく見ながら、必要に応じて検討してまいりたいというふうに思います。
また、漁業者の関係につきましては、私どもはもうちょっと出て、現場に行って話を聞いてこいというような御指摘かと思います。それにつきましては、できる限り、今まで漁協とは連携を取っていましたけれども、それも含めて、これからいろいろ努めてまいりたいというふうに思います。