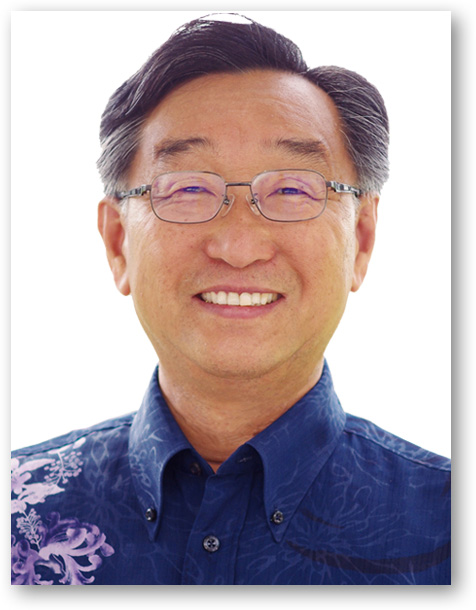質問・答弁を動画で視聴できます。
【概要】
(一問一答方式)児童館・児童クラブ事業の充実、発展を求めて
〇放課後の生活を保障する児童クラブは、面積基準の考え方を改め、もっと快適に
〇子どもの成長を見守り、支える児童館職員の処遇改善を
〇エアコン設置、ICT活用など、児童館の施設改善を急いで
〇子育て家庭を支援する児童館がさらに役割を発揮できる環境整備を
〇児童クラブの保護者負担金の減免をもっと広げて
〇すげの直子議員
日本共産党仙台市議団のすげの直子です。子どもの育ちにかかわる放課後児童クラブ及び児童館事業の充実、発展を求めて一問一答により一般質問いたします。
子どもたちの元気でにぎやかな声があふれる放課後の児童館。新年度早々、まだ落ち着かない状況の中、市内最大の326名の登録となっている富沢児童館をはじめ、この間数か所の児童館を伺ってきました。
「ただいま~」「おかえり」という、20年前の我が子の時と変わらない光景を目にして、心が温かくなりました。
子どもたちの放課後の生活が安全安心に、心地よく仲間と楽しく過ごせるようにと支援員の皆さんをはじめ、職員の方々が心を砕き実践されている様子をお聞きしてきました。いまや本市の児童クラブは、一小学校区で100人を超えているのが6割にのぼり、200人を超える登録となっている児童クラブが12校、300名以上が2校と児童数は年々増え続けています。今年度5月1日時点で111小学校区、112の児童館と92か所のサテライトがあり、1万3905人の登録と8年前の7173人から約倍で過去最高となっています。
ニーズが高まる中、一つの学校規模にもなっている児童クラブの子どもたちを毎日笑顔で迎え、安全に保護者のもとに送り出す営みに従事していただいている職員の皆さんに深い敬意を覚えずにはいられません。
放課後児童クラブは、保育を必要とする家庭とその子どもたちにとって、なくてはならない場であり、社会、経済活動を支える欠かせない事業です。
国においては、1998年に放課後児童健全育成事業として児童福祉法に位置づけられて以降、2007年には放課後児童クラブガイドラインの策定、2015年に運営指針がつくられるなど、事業を進めるにあたっての考え方や基準が示されてきました。
放課後の子どもの生活保障として、福祉施策として、法的に位置づけられ、必要な職員配置や専有面積、規模などの基準が示されてきたことは画期的前進です。小学6年生まで対象を広げるなど、量の拡充とともに質の向上も必要との考えに基づくものです。
本市においても国の流れに呼応して、条例の制定や事業に関する手引きなどを作成し、事業を推進してきました。条例に位置づけられ、様々な基準が作られ事業がすすめられるなら、それに比例して子どもたちや職員にとっては、より良い環境づくりが徐々に図られてしかるべきと考えますが、本市の児童クラブ事業のこの間の経緯と現状をどのように認識されているのか、市長のご所見を伺います。
このほど、本市社会福祉審議会に「児童館・児童クラブのあり方検討部会」が設置されました。肝心なのは、児童クラブは子どもの放課後や長期休暇中の生活の居場所として遊びはもちろん、休息を含めてゆったりと過ごすことができる快適性が必要です。信頼できる支援員が見守る中で仲間との生活や遊びを通じて一人一人の児童の成長・発達がしっかり保証される場でなければなりません。
そうした観点で、現状からどういう改善を図るべきか、そのことをよく検討し、今後の事業に反映しなければならないと考えます。
本議会の中でも児童クラブ事業については、様々な課題解決を求める議論が多数の議員から指摘されてきました。必要な人員確保の困難さや職員の処遇改善や研修の重要性、必要な面積基準の考え方、発達に障害がある子どもたちの受け入れのための体制整備や施設の改善などなど、多岐にわたる議論がされてきました。いずれも大事な点です。今後のあり方検討部会の中で真剣な検討の上、より良い改善がされるものと認識しています。
児童館・児童クラブのあり方検討部会の設置に至った経緯と検討する事項内容、またどういったスケジュールで進める予定なのか、お示しください。
本市の児童クラブ事業については、児童館事業の一つとして実施されてきました。児童館・児童センターは健全な遊びを通して子どもの健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした児童厚生施設、またはそれに準じた施設と位置付けられ、本来地域の乳幼児や中高生なども含め、18歳までを対象としている施設です。児童館が果たすべき役割や機能についてお示しいただくことを求め、伺って、ご答弁を聞いた後については一問一答で行います。
〇市長
ただいまのすげの直子のご質問にお答え申し上げます。
児童クラブ事業の経緯と現状、児童館の果たす役割等に係るお尋ねにお答えいたします。
児童館は、地域において児童に健全な遊びを提供し、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする施設でございます。
本市の児童館では、子育て支援の拠点として、遊びを通じた児童の健全育成、子育て家庭の支援、地域交流の推進、そして児童クラブ事業の主にこの4つの機能を有しております。
平成6年に小学校区ごとに1つの児童館を整備する方針を決定いたしまして、現在では、112館の児童館を運営をしております。
平成27年度の子ども・子育て支援新制度の開始にあたりまして、児童クラブ事業の運営の基準等を条例で定めましたが、この間、児童クラブの登録児童数の急増、児童同士の距離の確保などの課題が顕著となり、将来の方向性の検討が必要な時期にあるものと考えております。 児童の生活や、遊びの環境の改善等を通して、児童館が、地域に根差した身近な子育て支援施設としての機能を十分に発揮できるよう、取り組んでまいりたいと存じます。
〇子ども未来局長
児童館・児童クラブのあり方検討部会の設置に係るお尋ねにお答えいたします。
本市の児童館・児童クラブは、共働き世帯の増加や全学年への受け入れ拡大などを背景に、登録児童数が平成26年度以降で約2倍にまで急増し、児童クラブ以外の児童館機能の確保などが課題となっております。
こうした諸課題に対応しまして、将来的に持続可能なものとしていくため、児童館・児童クラブのあり方検討部会を設置し、検討に着手することといたしました。
この部会では、人口減少社会の中での児童館整備のあり方や、児童の居場所としての環境整備、児童クラブ以外の児童館機能の充実などについて、今年度から来年度にかけて検討を行ってまいります。
〇すげの直子議員
あり方検討部会での、具体的な検討内容について他にもあったかと思う、まず3点お示しをいただいたかと思いますが、それも含めまして検討の方向性について伺っていきたいと思います。
ご答弁にもありました、課題認識にあったように児童クラブの登録児童数の急増、クラブの大規模化がますます深刻です。一つの児童館、一サテライトに100人以上の児童が一緒に過ごすというのが常態化しております。
国が運営指針で示しております「子ども集団の規模」支援の単位はおおむね40人とする、となっております。この国の示す規模、どういった考え方から基準とされているのか、そのことと本市の状況について、どう認識しているのか、伺います。
〇子供未来局長
支援の単位の基準は、子どもが相互の関係性を構築し、集団としてまとまりをもって共に生活をしたり、職員が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人程度までが適当との考えで、基準とされております。
支援の単位ごとに放課後児童支援員を2人以上配置することとされており、本市におきましても、この考え方に基づいた対応を行っているところでございます。
〇すげの直子議員
例えばですね、以前伺った錦が丘児童クラブ、今年度の登録児童数が272名なんですけれども、本館以外のサテライトが一か所で172名が定員となっています。4つ以上の支援の単位が一つの建物内にあるということになっております。
先日、東京都文京区の職員で児童館の館長をされている方の講演を聞く機会がありました。「安定した関係を築ける範囲を超えた大人数になった際に起きる問題」として、子どものストレスを高める騒音、小競り合いと過剰な攻撃性、小集団化と親しい仲間以外への無関心、長い期間、過密な集団の中にいることによる感情のコントロールがとれなくなることなどを指摘されておりました。
先日伺った児童クラブの職員の方からは、たくさんの子どもがいる状況というのは、ただでさえ落ち着かないのに、まして支援が必要な子にとっては、ゆったり過ごすことができず、支援の度合いが高くなっていると感じる、とのお話もうかがってまいりました。それだけ、子どもたちにとってストレスが大きくなっているということです。
今、ご答弁いただきましてね、市も同じ考えでやっているというふうにおっしゃって、40人の一つの単位で人を配置したり、というふうにしているというふうにおっしゃるんですけれども、この施設内に境界があるわけでも、子ども同士が単位を超えて交流できないわけではないんですよね。1施設に150人、160人いれば、それがやはり一つの大集団というふうになって、職員一人一人はそのすべてにやっぱり目をくばらなければならなくなるという事だと思います。
やはり一か所の児童クラブは、支援の単位である概ね40人以下に近づけることがあるべき姿であり、そういった方向での努力が、私は必要ではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
本市の児童クラブでは、一か所に支援の単位が複数ある場合がございます。そうした場合でも、各諸室やスペースに分かれて、少人数で遊びや宿題などの活動をしております。その際には、空間及び時間帯を分けるなどの工夫もしながら、子どもたちが安全に充実した活動ができるよう努めているところでございます。
〇すげの直子議員
大規模な所に、たくさんいる所を是非、あらためて局長に行っていただきたいな、と思うんですけれども、その国が示している概ね40人以下っていうふうにね、示している意味、もう一度よくお考えいただきたいなと思います。
大規模化しているうえに、本市の児童クラブの必要な面積の考え方については、これまでも繰り返し指摘してきました。子ども一人につき、専用区画は1.65㎡以上の確保というのが国の示している基準ですが、本市の対応はどのようにしているのか、あらためてお示しください。
〇子供未来局長
本市におきましては、国が示す基準を参酌いたしまして、本市条例において、児童一人につきおおむね1.65㎡以上を基準としております。なお、算定にあたりましては、児童クラブ室と他の諸室の一部を専用区画とし、一日の平均利用人数を全体の75%と見込みまして、これを加味して計算をしているところでございます。
〇すげの直子議員
いろんな諸室も含めて、6割含めて、さらに実利用人数は75%として計算した上で、なので定員はここまで大丈夫だと現場に示すと、現場では定員数をめいいっぱい受け入れると。だから過密な詰込み状態になっている、というのが本市の状況だと思います。
やはりこうした面積の考え方は、この際改めなければならないと思いますけれどもいかがでしょうか。
〇子供未来局長
専用区画の面積に関する本市の考え方につきましては、児童クラブにおける課題のひとつと認識をしておりまして、今後、あり方検討部会で検討を行ってまいりたいと存じます。
〇すげの直子議員
子どもたち、学校という教育の場で長時間頑張ってですね、帰る場所が児童クラブです。ゆったりと安定した気持ちで、居心地よく過ごせる場、一人ひとりの子どもがその子らしく過ごせる場でなければならないのに、実態としては静養スペースすら満足に取れないというところもございます。早急に改善を図ることを強く求めておきます。
放課後の児童の保育、生活、成長の場として安定的に運営するためには専門的知識や経験を有した職員の確保が必須ですけれども、多くの児童館運営に携わる団体からは、この4月時点で昨年より多い161人もの欠員となっていて、誰かが倒れたら補充できないなど、深刻な状況を伺いました。
あり方検討で、人材確保・育成も検討内容になっているとのことですけれども、当局として、現時点でどうお考えなのか、伺います。
〇子供未来局長
児童館事業の安定的な運営のためには、十分な知識と経験を有する職員が、意欲を持って働き続けられる環境づくりが重要と認識をしております。
しかしながら現状では、保育士等の人材不足に加えまして、有期雇用の非常勤職員を多く採用していることが欠員につながっており、このことは課題ととらえております。引き続き、人材確保のための効果的な方策について、検討してまいります。
〇すげの直子議員
欠員が常態化していることを一刻も早く解消が必要です。そのためにはやはり処遇改善が必要だと思います。
有資格で熱意があっても、常勤より非常勤が圧倒的に多く、週30時間では月の手取り15、6万円程度で交通費が出ないなどの処遇では、やはり働き続けることはできません。
役割にふさわしい処遇となるように、国に求めるのはもちろんですけれども、市としても処遇改善、ぜひ図ることを求めますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
本市では、これまで国の補助制度を活用した処遇改善や、指定管理料を通じた各種手当などの改善を図ってまいりましたが、人材の安定的な確保につながる適切な処遇につきまして、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
〇すげの直子議員
ぜひ抜本的な改善を図っていただきたいと思います。
そういう現場が欠員状態では、職員の十分な研修の保障がなされているのかも心配なところです。
保育士等一定の資格要件を持つ方が認定資格研修を受ければ、放課後児童クラブの支援員としての資格が付与されることになっておりますけれども、力量を高めて現場の実践に生かすためには、継続的な研修での学びも必要不可欠だと思いますが、十分できているのか伺います。
〇子供未来局長
本市では児童館職員に対しまして、年間を通じて、現場で必要とされる知識やスキルの習得を目指した研修を実施しているところでございます。 多くの職員が専門性の向上を図れますよう、研修の動画配信を行い、それを視聴いただいたり、研修受講者による伝達研修を行うなど、学びの機会を今後とも提供してまいります。
〇すげの直子議員
いろいろ工夫していただきたいと思います。
施設の老朽化対策、より安全で快適に過ごせる環境整備についてです。
各諸室へのエアコン設置、進めておりますけれども、高天井の遊戯室についてはエアコン設置が進んでいません。場所によっては日当たりがよく、夏の暑さは危険なほどにもなるということです。児童クラブの子どもたちが、夏休み中も一日過ごす場であり、地域の子どもたちが安全に遊べる空間であることが必要です。遊戯室へのエアコン設置を急ぎ進めるよう求めますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
各居室へのエアコン設置につきましては、天井の低い遊戯室も含め、設置をほぼ完了しておりまして、高天井の遊戯室についても、一部の施設では設置済みでございます。今後、順次、設置が進むよう検討してまいります。
〇すげの直子議員
ぜひスピードアップして、急いで付けていただきたいと思います。
「保護者負担金の適正化」も検討内容に入っていると伺っております。
まず、現在の負担金と減免の内容、どのくらいの方が減免対象になっているのか、お示しください。
〇子供未来局長
負担金は、登録児童一人あたり月3,000円としておりまして、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯、所得が急減した世帯は全額免除、その他の所得税非課税世帯は半額免除としております。
令和2年度の減免対象者は、全額免除が756人、半額免除が78人、計834人となっており、その割合といたしましては6.3%でございました。
〇すげの直子議員
それ以外に延長料金は1000円かかるということもあると思いますが、今お示しいただきました、全体のたった6%しか減免適用になっていないと。生活保護世帯とか住民税、所得税非課税世帯のみ、これでは対象があまりにも狭すぎます。他都市でも実施しているように就学援助利用世帯や多子減免など、対象を広げるべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
あり方検討部会におきまして、保護者負担金の適正化について議論する中で、減免制度の対象やその内容につきまして、他都市の事例なども参考にしながら検討してまいりたいと考えております。
〇すげの直子議員
さらに「適正化」の問題です。
以前は独自に保護者会などをつくって、おやつ代などを集めていたことはあったんですが、児童クラブは当初無料でした。
2012年から有料化され、現在に至っていますが、子どもたちのおかれている環境は無料だった時からどのような改善がされたと認識しているでしょうか。
そして、現在の保護者負担金が適正ではないと考える根拠についてお示しください。
〇子供未来局長
負担金の導入にあたりましては、児童クラブ室等へのロッカーやエアコンの設置など、設備の充実を行ったところでございますが、これまで必要な活動スペースやサテライト室等の確保も進めてまいりました。
保護者負担金については、国の考え方として、保護者の負担が5割、残りを国・県・市により負担することが目安として示されております。本市では保護者負担金の占める割合が、負担金導入時には2割程度となっておりまして、その適切な比率について、今後検討してまいりたいと考えております。
〇すげの直子議員
札幌市とか大阪市とか川崎市など政令市の中でも、今も無料で実施されているという都市もございます。今のですね、ロッカーとかエアコン設置というお話、それは子どもがいる環境整備としては、もはや当然の、市としてやらなくちゃいけない仕事だと思うんですけれども、今の詰込みと言えるような大規模、過密な状況のままで、とてもこれ以上ですね、引き上げるわけには私はいかないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
利用登録児童の増加や、コロナ禍に伴う感染拡大防止の観点から、そうしたことからも児童クラブにおける児童の適切な距離の確保については、課題として認識しております。
今後、あり方検討部会におきまして、児童の生活の場・遊び場の環境改善という視点から議論を深め、こうした課題への対応について検討を進めてまいります。
〇すげの直子議員
環境改善を抜本的に図ることこそ、早急な課題だと申し上げておきます。
先日伺ったある児童館の館長さんからは、「私たちがしっかり見守り関わりたいと思っている子供が児童クラブを辞めてしまう。一つには、提出する書類の準備を保護者が大変で諦めてしまうということがあると感じる。あの子は放課後どこでどう過ごしているのか、手を離してはいけなかったのではないかと思うんです」というお話をお聞きしました。
児童クラブも保育所と同程度の書類の提出が求められるようになっていますが、以前はこんなに必要ではなかったはずです。少しでも簡素化するなど、本当に必要な方が漏れることのないよう支援を強化すべきです。
また、負担金の滞納があると、翌年申込みができないということになっています。未納の原因を把握して支援につなげることこそ必要であり、排除することなどあってはならないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
負担金につきましては、保護者の収入状況に応じた減免を行っており、納付をしておられる保護者の皆様との公平性の観点から、滞納がないことを登録の要件としております。
なお、未納世帯から御相談があった場合には、未納に至った状況などを丁寧に伺いまして、支援が必要な場合には適切な機関につなぐなど、今後とも必要な対応を行ってまいります。
〇すげの直子議員
保育所では、滞納に陥ってしまっている人が入れないということはありません。ぜひ、その枠組み、制度の改善を強く求めたいと思います。
お迎えがあることで、家庭との接触も多いのが児童館です。実際、子育て環境充実調査特別委員会で、児童館を運営する有識者からも、おにぎりの作り方が分からないという保護者に寄り添って関わる中で、子供がおにぎりを持ってこれるようになったなどの具体的なお話もお聞きしました。児童クラブでの子供の様子、日々の保護者の方々とのやり取りから、様々な困難を抱えた御家庭があり、支援の必要性が高まっているとのお話、どこでも指摘されています。
子供の貧困の解決、本市でも重要な施策の一つとしています。サインを見つけることができる児童館の皆さんには、そうした視点で今後も頑張っていただきつつ、行政や学校、民生委員など、地域を含め、より連携を強化しながら支援を強める必要があります。そして、その際も、児童館任せではなく、行政がしっかりと役割を果たすことを求めますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
支援が必要な御家庭に対しては、小学校や区役所、児童相談所、アーチルなど、関係機関と連携をして対応を行っているところでございます。
こういった連携による支援の実例につきまして、研修などの機会を通じて共有するなど、今後とも児童館と行政とが協力をし、それらの役割を果たしてまいります。
〇すげの直子議員
現場の方々からのお話をお聞きして、児童館、児童クラブが本当に大事な役割を担っていただいていることを改めて実感してまいりました。
第一問で、児童館の果たすべき役割について御答弁いただきました。この間、児童クラブが大規模化する一方で、児童館としての地域での機能発揮が困難になっていることも、残念ながら起こっています。依然として、自由来館については週末の土曜日にしか実施できない状況です。児童クラブの子供たちが朝からいる長期休暇中には、乳幼児の受入れが難しい。中高生たちも含めて、居場所の提供、健全育成としての役割の発揮が求められていますが、実際の現場では、そうした事業の充実まで到底かなわないというのが実態です。
児童館事業と児童クラブ、どちらも子供の健全育成には欠かせない事業です。それぞれしっかり充実させることが大切だと考えますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
現在までに児童クラブ事業の比重が高まり、また感染症の影響も相まって、他の児童館事業に影響を与えていることにつきましては、課題と認識をしております。
今後、児童館の4つの機能である児童クラブ事業、児童の健全育成、子育て家庭支援、地域交流の推進といったそれぞれを充実させるための方策について、検討を行ってまいります。
〇すげの直子議員
それぞれ充実させたいという御認識はあるということです。
私たちは、そのためにも、放課後児童クラブは児童館事業の一つという位置づけでその中に何とか押し込もうとするのではなくて、独立した一事業として実施するように、かなり以前から提案してきました。これだけサテライトが増えていることを考えると、もっと早い段階からそうした決断をしていれば、今の児童館、児童クラブに見える光景は大分違ったものになっていたんではないかというふうに悔やまれます。
児童クラブの大規模化が進む中で、児童クラブの課題解決もままならない、そして、そのことが児童館としての機能発揮にも影響が及んでいる状況が続いています。児童館が地域の子育て機能の役割を果たすためにはどうあるべきなのか、そして、放課後児童クラブが子供たちの成長、発達の場としてどうあるべきか、それぞれの事業として充実させるために、どういう在り方がふさわしいのか、これまでの形態にのみとらわれることなく、ぜひ検討を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
〇子供未来局長
本市におきましては、小学校区ごとに児童館を整備し、児童クラブ事業を実施してまいりました。地域の中にある子育て支援の拠点として、日常的に児童や乳幼児親子が集い、また、様々な世代の方々が交流する場である児童館が小学校区ごとに設置されているということは、本市の強みでもあると考えております。
今後も、このような利点を生かしつつ、児童館事業の在り方について検討してまいります。
〇すげの直子議員
いろいろ質問をさせていただきました。課題ははっきりしていると思いますし、解決の方向性も明らかになってきているのではないかなと思います。
ご当局や部会の皆さんはもちろん、郡市長にも、そして、ここはぜひ財政出動にも関わる財政局長とか含めて、ぜひとも現場に足を運んでいただいて、子供たちが日々過ごしている様子、ぜひ直接見ていただきたいと思います。特に財政局長にご答弁は求めませんけれども、ぜひ市長、先頭に立って現場にぜひ行っていただきたいということで求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
〇市長
児童館における課題の把握、それからまた今後の方向性の検討のために、子供たちの活動の様子をじかに見たり触れたり、そしてまた乳幼児親子や職員の皆様の声を伺ったりするというのは、とても重要だというふうに思っております。
これまでも私も児童館にお邪魔をさせていただきましたけれども、今後もそうした機会を大事にしながら、児童館が、子供たちが安心して遊ぶことができて、そしてまた乳幼児親子にとっても楽しく過ごすことができる、そんな地域の子育て支援拠点であり続けられるように、検討を進めてまいりたいと存じます。
〇すげの直子議員
現場では、本当にたくさんの子供たちを受け入れて、本当に事故が起きないようにということで、毎日、本当に気を配りながら対応していただいております。児童館、児童クラブ事業、抜本的な改善を図るよう、最後に強く求めて、一般質問とさせていただきます。