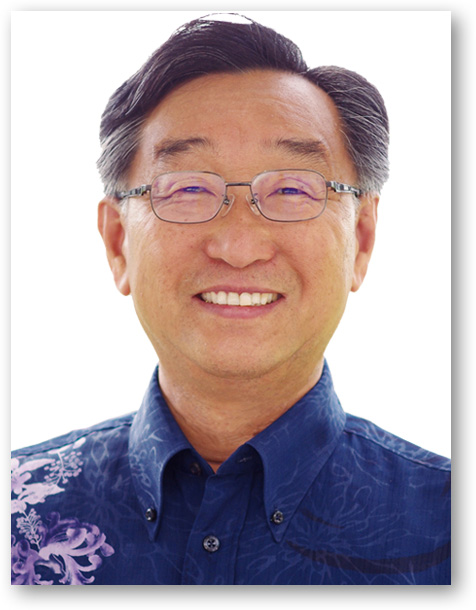質問・答弁を動画で視聴できます
【概要】
〇コロナ対策の引き続く強化・充実を
〇空気感染対策の重要性
〇クラスターが増加している高齢者施設への対策と支援を
〇保育所や学校の児童を経由した感染への対策を
〇省エネにもなる全熱交換換気扇の考え方
〇高村直也議員
日本共産党の高村直也です。新型コロナ感染症対策に関わって一般質問いたします。
政府はコロナの感染症法上の分類を、今年5月8日から「5類」へ移行する決定をしました。
このことでコロナ患者や医療機関への支援、ワクチン接種、検査などへの財政支援が打ち切られようとしています。対策が後退すれば感染状況が悪化しかねませんし、医療費への公的支援が縮小すれば、受診控えも予想されます。政府はコロナに対応可能な医療機関が増えるとしていますが、もともと無理してコロナ病床を確保してきた医療機関でかえって病床が減ることが懸念されます。対策を自己責任とすべきではありません。
本市のコロナ感染者数は、昨年12月に1か月あたりで過去最高の4万8988人となりました。この月はコロナ関連の死者数も現在確認しているだけで94名と過去最高です。12月27日には、仙台医療圏の受け入れ可能病床数は92.7%、確保病床数は71.4%とひっ迫しました。
現在コロナ第8波は収まりつつありますが、アメリカで猛威をふるっている新たな変異ウイルス「XBB1.5」も国内で見つかっており、感染拡大の波は今後も予想されます。
こうした中、感染状況や医療現場の実情など、科学的な根拠を基づくのではなく、日程ありきで5類への引き下げを決めたことは拙速と言わざるを得ません。新たな感染拡大や医療のひっ迫、多くの人命を危険にさらす事態になりかねません。
コロナ対策を後退させず、さらなる強化と拡充が求められますが、いかがご認識でしょうか。
ふりかえりますと、コロナ禍が始まったばかりの頃と現在とは様相が変わっています。
コロナウイルスは変異を重ね重症化リスクが下がる一方、感染力が高まっています。
基本的な感染症対策、検査やワクチン接種も進みましたが、それでもコロナ収束の兆しが見えません。当初はワクチンにより集団目根気を獲得すれば新規感染者が激減し、収束するとの見通しもありました。しかし次々に新たな変異ウイルスが現れ、免疫逃避能力も高まるなど、単純にいかない状況です。
感染症対策の考え方も発展してきました。
感染経路には大きく分けて、接触感染、飛沫感染、空気感染があります。接触感染とは、ウイルスに汚染されたものを触れた手で目や鼻を触ったり、物を食べたりすることで起こる感染です。飛沫感染とは、会話やくしゃみなどの際に飛び散る細かい水滴にウイルスが含まれており、それが目、鼻、口から取り込まれて起こる感染です。
飛沫は水分を含んでおり、重力で落ちます。ソーシャルディスタンスが2mとされているのも、重力で飛沫が届かない距離だからです。
これに対して空気感染とは、飛沫よりもずっと小さいウイルスを含んだ微粒子が落ちることなく空気中をただよい、人体に取り込まれて感染するものです。
厚労省はこれまで〝エアロゾル感染を疑う事例の増加は確認されておらず、感染経路は主に飛沫感染と接触感染と考えれる〟と述べていたこともありました。しかし昨年7月14日の新型コロナウイルス感染症対策分科会では「エアロゾル対策が必要」だとして、換気対策などの位置づけを高める提言が出されています。10月にも同様の提言が出ています。
WHOのホームページにあるQ&Aでも「換気の悪い、あるいは人が密集した室内ではウイルスが拡がる。なぜならエアロゾルは空気中を漂い続けることができ、会話の距離よりも長い距離を移動できるからだ」とされています。
国内では専門家から、主たる経路は空気感染である、とする見解がさまざまに出されています。
コロナ対策では、主要な感染経路である空気感染対策を重視して取り組むべきですが、いかがでしょうか。
空気感染対策が重要という観点に立つと、対策のあり方も変わってきます。
接触感染対策は手指消毒やテーブル、ドアノブの消毒などを行うものです。飛沫感染対策は、マスク着用やアクリル板の設置、大人数での食事の機会を避ける、などです。一方空気感染対策では、空気そのものを入れ替える、換気が最もシンプルで効果的な対策になります。
換気が十分にできない場合は、hapaフィルター付き空気清浄機で微粒子をキャッチする方法があります。
サーキュレーターで空気の流れをつくることも有効です。アクリル板やパーティションは空気の流れを妨げるデメリットがあることを認識する必要があります。
またマスクでは大きな飛沫を防げても、小さな微粒子を防ぎきれません。完全に防ぐなら微粒子も通さない、N95マスクが必要になります。
口を開かなければ飛沫は飛びませんが、微粒子は鼻呼吸でも広がります。
空気感染対策の観点から、本市のコロナ対策の取り組みについて、お示しください。
感染拡大を抑止する上での「急所」とされてきたのは、当初飲食店でしたが、今は高齢者施設や学校、保育所などとされています。
実際に本市内でも高齢者施設でのクラスター発生件数は、令和2年度に11件、3年度に22件、今年度は1月までに41件と、毎年約2倍に増えています。本市の65歳以上のコロナ死者数は、令和2年度に9名、3年度に49名、今年度は1月までに276名と急激に増えています。
また子育て世代が、子どもを経由して感染する事例をたくさん聞いています。市内のある病院では第8波の感染者のうち、約6割が子育て世代にあたる30代、40代だったとのことです。多くの福祉施設などからも同様の実態をお聞きしています。
高齢者施設、学校、保育所などでの感染症対策を改めて強化すべきと考えますが、市長の認識を伺います。
高齢者施設では「利用者が感染してしまったら命にかかわる重大な事態だ」「ただでさえ人手不足の中、職員が感染してしまったら、どう埋め合わせすればよいのか」など、職員のみなさんは日々神経をとがらせています。
また認知症などのため、「陽性者なのに、きちんとマスクをつけてくれない」「ゾーニングをしても陽性者がエリアを越えて移動してしまう」という実態があり、対策には困難がつきまといます。
本市では高齢者施設などに対し、感染症対策の助言と指導を行う専門家を委員とした、仙台市感染制御地域支援チームを設置しています。。同チームは高齢者施設で陽性者やクラスターが発生した場合、現場におもむいて助言と指導を行っています。
高齢者施設での対策について、最前線で活動する同チームの取り組みと今後の課題についてご認識をお示しください。
ある施設からは「医療がひっ迫する中で陽性者が出た場合、基礎疾患があり重症だと伝えると入院を断られるケースが多い。酸素吸入が必要な方など、一刻を争う場合には、救急車を呼ぶくらいしか手段がない」と切実な実態をお聞きしました。県と本市で運営する医療調整本部も衣料がひっ迫するもとでは、入院先の振り分けに困難をきたし、入院まで数日待たされる事態が発生しています。
施設で感染者が出た場合、早期に確実に治療、療養できる体制の構築が求め得られます。施設内の医療的ケアを支援するチームを派遣する体制をつくるとともに、入院先となるコロナ病床のさらなる確保を進めるべきですが、いかがでしょうか。
今年の冬は寒波を経験しましたが、「隙間風が入り、寒いから窓を閉めてほしい」と言われ、困ったとのお話を聞いています。熱中症対策や寒さ対策も命と健康に関わる大事な取り組みであり、窓を開け換気には困難がともないます。
そうした中、全熱交換型換気扇の導入が求められます。全熱交換型換気扇とは排気と給気を別々におこない、それらの空気を仕切りを介して接触させ、温度を損なわず空気だけを入れ替える設備です。
感染症対策と熱中症などへの対策を両立し、省エネにもつながります。
厚労省はこうした換気設備の導入に補助金を出していますが「通常の換気ができる場合には補助対象外」としており、条件が狭く、ほとんど利用されていません。
環境省は令和3年度に高機能換気設備に補助金を出していましたが、現在は打ち切られています。
高齢者施設の実態を鑑み、厚労省の補助金の対象拡大や環境省の補助金の復活を国に求めるべきですが、いかがでしょうか。
また本市でも施設への全熱交換型換気扇の導入に助成をおこなうべきですが、いかがでしょうか。合わせて伺います。
コロナに加え、物価高騰、電気料金と燃料費の高騰が高齢者施設の経営を圧迫しています。
介護報酬は公定価格で決まっており、高齢者施設の経営努力で収益を上げることは困難です。高騰の影響は、ほぼそのまま赤字となってしまいます。
さらに職員がコロナに感染すれば、訪問介護では担当の職員が現場に行けないぶん、収益減になります。通所や入居の場合には、配置基準の緩和がされているので職員の人数が減っても、これまで通り利用者を受け入れられますが、たくさんの仕事を少人数でこなさなければならず、苦労を強いられます。濃厚接触者に休業を取らせるなど、職員が空白となることによる疲弊は大きなものがあります。介護職員は社会機能維持者ですので待機期間の3日目から解除可能ですが、施設に感染を広げないよう、単純に職場復帰できないのが現状です。コロナで入院する利用者が出てしまうと、そのベッドは空けたままにせざるを得ず、減収につながります。
高齢者施設を応援するため、本市として慰労金の支出に踏み出すべきではないでしょうか。伺います。
本市が取り組んできた高齢者施設への支援制度としては、昨年7月1日から3月31日までを対象として、食料品と電気・ガス等の値上げ分を補填するものがあります。しかし4月以降は何の支援もありませんし、これらの制度でも料金の値上げを十分にカバーできず、大幅に減収しているとお聞きしています。
高騰する電気代などへの支援を拡充し継続するべきですが、いかがでしょうか。
続いて学校における対策についてです。
十分な換気ができるかどうか、公共施設低炭素化検討事業の一環として幸町南小学校で実証実験がおこなわれてきました。
現在文科省は、換気によりCO2濃度を1000ppm以下とするよう推奨しています。しかし実証実験では令和2年9月に、窓開け換気のみおこなった場合にCO2濃度が最高で3500ppmとなり、連日のように1000ppmを超える結果となりました。これに対して全熱交換型換気扇を導入した令和3年9月の実験では、ほぼ毎日1000ppmを下回る結果となりました。
そもそも窓を開ければ、十分な換気ができる保障はありません。風の強さにも左右されますし、窓を何センチ開けるか、などが徹底されてもいません。
十分な換気ができるかどうか、客観的に確かめるにはCO2センサーを利用する方法があります。
すでにCO2センサーは市立小学校118校のうち、校内に1台以上設置している学校が82校、全普通教室に設置している学校が32校にのぼっています。市立中学校では64校中1台以上設置が52校、全普通教室設置が26校となっています。
CO2センサーの精度は製品によってまちまちですが、数万円程度のものでも測定値の5%に加え、プラスマイナス50ppm程度の誤差とされています。およそ1000ppmを下回っているか否かを確かめるには十分です。
まずはすべての学校に1台以上のCO2センサーを導入してはいかがでしょうか。
全熱交換型換気扇については、新築の学校ではすでに導入されています。実証実験によれば窓を開け換気よりも、確実に十分な換気が出来ると考えられます。
ウイルスを含んだ空気がしっかり排気されるよう、全熱交換型換気扇のフィルター清掃を徹底すると同時にCO2センサーで客観的な検証を行いながら適切な運用を促すべきと考えますが、いかがでしょうか。
さらに全熱交換型換気扇のない学校については、CO2センサーで検証した結果、十分な換気が困難と考えられる場合には取付工事の必要のない空気清浄機を積極的に導入してはいかがでしょうか。伺います。
続いて保育所等における児童の感染症対策についてお聞きします。
保育所はマスクの着用やワクチン接種が難しい子どもたちが多く、密が避けられない環境です。こういう中だからこそ、換気対策を充実すべきです。
CO2センサーは公立保育所に、まだほとんど導入されていないとのことです。学校ではすでにたくさん導入されているのですから、子育てのよりどころとなる公立保育所ではすべての施設に1台以上導入すべきですが、いかがでしょうか。
また全熱交換型換気扇を導入し、空気清浄機も全ての保育室に1台ずつ導入してはいかがでしょうか。伺います。
私立の保育施設にも対策が求められます。
保育施設におけるCO2センサーや空気清浄機を含む物品購入にあてることができる、厚労省の補助金がありますが、来年度から物品購入が対象外となります。この補助金は50万円が上限で、コロナ対策に伴う超過勤務や休日勤務手当などにも充てられていますので、実態としては空気清浄機などの購入に十分充てられていない可能性があります。
国に対し、この補助金を継続するとともに全熱交換型換気扇も対象となるよう、求めてはいかがでしょうか。
また本市としても、CO2センサーや全熱交換型換気扇、空気清浄機の導入に助成をしてはいかがでしょうか。
最後に伺って第一問といたします。
◯市長(郡和子)
ただいまの高村直也議員の御質問にお答えを申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する感染対策に係る御質問にお答えをいたします。
今般、政府において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが見直され、5月8日から五類感染症として位置づけられることとなりました。私といたしましては、この位置づけの見直しがコロナウイルスのこの病原性や感染力など、これまでの知見に基づいた判断であって、現在の感染状況なども踏まえて、まず妥当なものと認識をしているところでございます。
高齢者施設や学校などについては、施設ごとに感染対策マニュアルが策定されて、それに基づき感染対策が取られております。
今後、医療提供体制や医療費の公費負担などについては、3月上旬に具体的な方針が国から示される見込みであり、施設ごとの対策の見直しも図られるものと考えております。
引き続き、位置づけの変更以降においても、医療を必要とされる方が適切な医療を受けられることが重要であるとの考えの下、市民の皆様や医療機関における混乱を招くことがないよう、県や市医師会をはじめ関係機関と連携して適切な対応に努めてまいりたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、関係の局長から御答弁を申し上げます。
◯健康福祉局長(加藤邦治)
私からは、新型コロナウイルス感染症対策に関する御質問のうち、市長からお答えした以外の当局所管分につきましての御質問にお答え申し上げます。
初めに、新型コロナウイルス感染症の空気感染対策についてでございます。
感染対策として、空気感染のリスクを下げるため、小まめな換気は有効であるものと認識しており、関係部局と連携し、高齢者施設や学校などの各施設に対し、効果的な換気等について周知を図ってきたところでございます。
また、換気に加え、サーキュレーターによる空気の循環も有効であること、3密の回避、手洗いといった基本的な感染対策も重要であることから、引き続きこれら感染対策の周知啓発に取り組んでまいります。
次に、仙台市感染制御地域支援チームの取組と課題についてでございます。
このチームは、高齢者施設等に感染対策の助言等を行うため、クラスター発生施設等に対し、これまで訪問指導を126回実施、うち高齢者施設には99回実施をしております。
訪問したチームからは、感染対策等の事前準備が不十分であったとの指摘もいただいており、施設において、クラスター発生等を想定した日頃からの備えが必要になるものと考えております。
次に、高齢者施設への医療的ケアを支援するチームの派遣と病床の確保についてでございます。
施設における医療的ケアを支援するチームの編成は、医師等の人員確保の点から困難でございましたが、状況に応じて医療調整本部と連携し、ケアつきの宿泊療養施設での療養や入院につないでまいりました。
また、入院病床につきましては、入院設備を持つ病院の主要病院長等による会議の中で、病床の確保についてお願いし、拡充を図ってきたところでございます。
今後も必要な方が必要な療養ができるよう、県や関係機関と連携し、感染状況に応じた適切な対応に努めてまいります。
次に、高齢者施設における換気設備の国補助の拡大等についてでございます。
高齢者施設において、熱中症などに配慮しながら換気を行うことのできる全熱交換型換気扇を導入することは、感染症対策としても効果があるものと認識しております。
高齢者施設への設備導入に関しては、これまでも他の自治体同様に、国補助事業の活用を基本としております。この間、本市ではそうした設備の導入に係る具体の御相談や要望はお受けしていない状況にございましたが、引き続き、事業者からの御意見等も踏まえながら、必要に応じて国への働きかけなどを検討してまいります。
次に、高齢者施設に対する慰労金についてでございます。
新型コロナウイルス感染症により減収となった施設に対しては、感染を理由とする利用者数の減少の影響が大きい一部サービスにおいて、引き続き、特例の加算が適用される見通しとなっております。
また、感染により生じた通常には想定されない掛かり増し経費等に対しては、県を実施主体として、緊急雇用に係る費用や割増し賃金等の補助事業が実施されているところでございます。
今後とも、こうした加算や補助制度等が活用されるよう周知に努めるとともに、感染症による影響を注視しつつ、事業者の声も伺いながら、必要に応じて国への要望等を検討してまいりたいと存じます。
最後に、高齢者施設を対象とした物価高騰対策についてでございます。
本市では、原油価格をはじめとする物価高騰が継続する中においても、事業者が安定的に福祉サービスを提供できるよう、国の財政支援も活用しながら、高齢者福祉施設の食材料費や燃料費等に係る助成を数次にわたり実施してきたところでございます。
今後とも、物価変動等の状況や国の対策等の動向も注視しつつ、事業者等の実情等もお伺いしながら、引き続き検討してまいります。
◯子供未来局長(小林弘美)
保育所等における感染症対策についてお答えいたします。
まず、公立保育所へのCO2センサー等の導入についてでございます。
公立保育所の換気対策につきましては、日頃からの小まめな換気のほか、一部の保育所でCO2センサーを活用しております。また、空気清浄機については、全ての保育所で設置しており、全熱交換型換気扇につきましては、大規模改修工事の際に導入を進めているところでございます。
感染防止には、効果的な換気対策が重要と認識をしており、引き続き、様々な取組を実施しながら、コロナ感染対策の徹底を図ってまいります。
次に、民間保育施設への補助についてでございます。
本市では、これまで国の補助金を活用し、空気清浄機等の備品購入や、消毒作業に伴う職員の超過勤務手当等に対し、助成を行ってまいりました。また、今年度には、指定都市市長会を通じ、換気設備の設置に対し財政措置を講じるよう、国への要望を行ったところでございます。
来年度につきましては、これまでの補助実績や昨今のコロナウイルス感染症をめぐる状況等を踏まえ、国の補助金が見直され、備品購入費用が補助対象から外れる見込みとなっておりますので、本市でも国の方針に合わせ助成を行ってまいります。
今後は、国の動向等を注視しながら、状況に応じて国への要望を行ってまいりたいと存じます。
◯教育長(福田洋之)
学校における感染症対策についての一連の御質問にお答えをいたします。
CO2センサー及び空気清浄機に関しましては、こうした機器も導入できるよう、感染症対策の予算を各学校に配当し、その中で各学校が実情に応じて講じているところでございます。今後、機会を捉えて、教育委員会から各学校に対し、さらなる導入を促してまいりたいと存じます。
また、全熱交換型換気扇が導入されている学校におきましては、機器の適切な管理に努めるとともに、窓開け換気と併用して、効果的な換気ができるよう対応してまいります。
今後も、これらの取組などを通じまして、学校における感染症対策を行うことで、適切な教育環境の確保に努めてまいりたいと存じます。
◯高村直也議員
御答弁ありがとうございました。二点再質問をいたします。
まず一点目は、高齢者施設で職員さんが陽性になった場合の慰労金についてです。
今御答弁がありまして、国への要望の中で入れていくですとか、あるいは今現行でも県や国の補助金があるといったお話がありましたけれども、しかし、今現に、5類になって、支援もこれからどうなるか分からない局面ですけれども、高齢者施設では実際にクラスターが増えるという深刻な問題があるわけです。65歳以上の死者数もどんどん増えている中にあります。
そういう意味では、コロナ収束どころか、質的にも量的にもこれまでよりも大変な状況があるわけです。そういう中で、収入の減少も強いられているわけですし、国や県の補助金も活用されていますけれども、それでも大幅な減収となる実態があるわけです。コロナ対策を進める上で重要な高齢者施設を応援するために、本市として慰労金の支出に踏み出すべきではないでしょうか。改めて伺います。
二点目に、公立保育所のCO2センサー導入についてです。
空気清浄機については、各施設1台以上あると。そしてまた、ほかの機器についても総合的に準備していくというふうな御答弁だったと思うんですけれども、御答弁の中にもありましたけれども、公立保育所にこのCO2センサーというのはほんの一部しか導入されていないというふうな状況にあるわけです。そしてまた、せめてこのCO2センサーを各施設1台以上導入してほしいということを私申し上げたわけですけれども、それに対する明確な御答弁がなかったわけです。
空気清浄機が各保育施設に1台以上あるから大丈夫かというと、そうではなく、例えば1台では全ての保育室に置くことができないわけです。ウイルスを取り除くことができないわけです。つまり、換気対策として、結局はシンプルな窓開け換気しか行っていない保育施設がたくさんあるということなんですね。そういう窓開けの換気には、十分に空気を入れ替えることができているかどうか分からない、できているとは限らないということが、実際に幸町南小学校の実証実験で示されているわけなんですね。ですから、そういう状況をどうするのかということがあるわけです。厚労省もCO2センサーを推奨しております。費用も安くて、工事なども必要ありません。各保育施設に一個あれば、各保育室に回して使うこともできるわけです。
ですから、全ての保育所にせめて一台以上のCO2センサーを導入すると、はっきり申し上げていただきたいと思いますけれども、再度伺います。
◯健康福祉局長(加藤邦治)
施設への慰労金に関連する再度のお尋ねでございますけれども、施設における減収等につきましては国等で制度を持っておりますほか、また様々な補助制度も現在設定されているところでございます。私どもといたしましては、各施設がその実情に応じてこういった加算なり補助なりを活用できるように、引き続き努力をしてまいりますとともに、またそういった中でも施設の状況等を詳しく伺いながら、必要に応じて国への要望等も行ってまいりたいと存じます。
◯子供未来局長(小林弘美)
公立保育所へのCO2センサー等の導入につきまして、再度のお尋ねにお答えをいたします。
現在、公立保育所の換気対策につきましては、CO2センサーですとか、空気清浄機、また全熱交換型換気扇などを様々保育所の状況に応じまして導入をしているところでございます。
現在は、CO2センサーの活用につきまして、新たな予算を獲得して対応していくというようなことは考えておりませんけれども、なお効果的な感染対策が重要ということにつきましては認識をしておりまして、様々な対応を組み合わせながら今後もコロナ感染対策の徹底を図ってまいりたいと考えております。